ヨコハマアートサイト、演劇ワークショップの助成金を申請していましたが、今年も100万円、満額回答でした。


3年連続100万円ゲット!です。とりあえずホッとしました。ただワークショップの費用は全体で200万円をちょっと超えますので、あと100万円をどこかで調達しなければなりません。それがすごく大変。
演劇ワークショップの企画が、「芸術性」「地域協働」「将来性」「実現性」「収支バランス」等、すべての審査ポイントで100点満点で評価されたことは、とてもうれしいです。
申請書の「事業のねらい」には
障がいのある人たちと一緒に新しいものを創り出す関係を作り、そこから芝居を起こしていく。彼らがいてこそできる芝居は、いっしょに生きる理由を明確に表現する。それを社会に発信することが大きなねらい。
といったことを書きました。
「彼らがいてこそできる芝居は、いっしょに生きる理由を明確に表現する。」
そのことにつきると思います。舞台に上げる芝居は、いっしょに生きる理由そのものであり、いっしょに生きると何が生まれるのか、何を創り出せるのかを、明確に示します。
「共に生きる社会を作ろう」とか「共生社会を作ろう」という声はあちこちで聞きますが、そこで何を作り出すのか、明確に提示しているところは聞いたことがありません。一番大事なところが、みんな曖昧なのです。
神奈川県は「ともに生きる社会かながわ憲章」を作り、様々なキャンペーン活動をおこなっていますが、「ともに生きる社会」が実際何を作り出すのか、一向に見えてきません。ものすごいお金を使っているのに、どうして一番大事なところを表現できないのかと思います。
結局は、本気でそれを作ろうとしていないんじゃないか、と思ってしまいます。
芝居は本気にならないと作れません。言葉だけのお遊びをやってては舞台に上げる芝居なんかできません。
障がいのある人たちといっしょに、お互いの思いを表現のかたちでぶつけ合います。ぶつけてもぶつけても先がなかなか見えてきません。本番の舞台の直前まで、バトルが続きます。
そうやってようやく舞台に上げる芝居ができあがるのです。だからこそ、舞台が輝くのです。
2020年1月25日(日)の午後、みどりアートパークホールの舞台で発表します。みどりアートパークは横浜線長津田駅前です。

第六期演劇ワークショップの参加者を募集します。取り上げる素材は宮澤賢治『どんぐりとやまねこ』です。ワークショップの日程は8月17日(土)、9月21日(土)、10月19日(土)、11月16日(土)、12月14日(土)、2020年1月18日(土)、1月25日(土)、1月26日(日)です。時間は9時〜16時くらい。場所はみどりアートパークリハーサル室。舞台発表の1月26日(日)は17時半頃まで。毎回お弁当、お茶持ってきてください。参加費は大人1000円、子ども500円です。参加希望の方は参加理由も書いて応募してください。今年はかなり参加希望が多いので、参加理由を見て決めたいと思います。会場のキャパシティの関係で、募集は15人くらいです。ぷかぷかさん15人、地域の人15人くらいの構成で行きます。
メールの送り先はtakasakiaki@blue.plala.or.jp 高崎です。




 クラウドファンディングも考えつつ
クラウドファンディングも考えつつ いつか実現したいです!させます
いつか実現したいです!させます




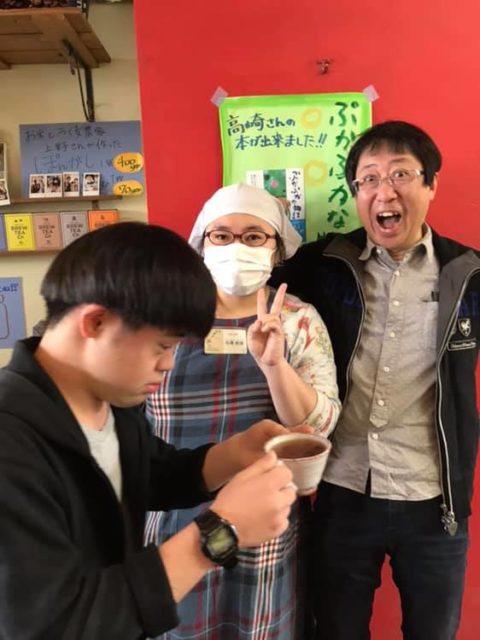






 」という、共生社会よりも一歩先を行った考え方だと思います。生産性がなくても、手がかかっても、そのままでいい。世の中をほっこりさせる必要な存在なんだよ!ということが、もっと広がって行けば良いと、心から思いました(^o^)
」という、共生社会よりも一歩先を行った考え方だと思います。生産性がなくても、手がかかっても、そのままでいい。世の中をほっこりさせる必要な存在なんだよ!ということが、もっと広がって行けば良いと、心から思いました(^o^)






