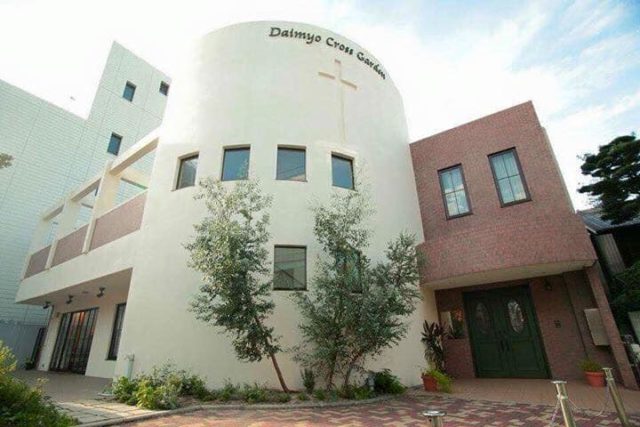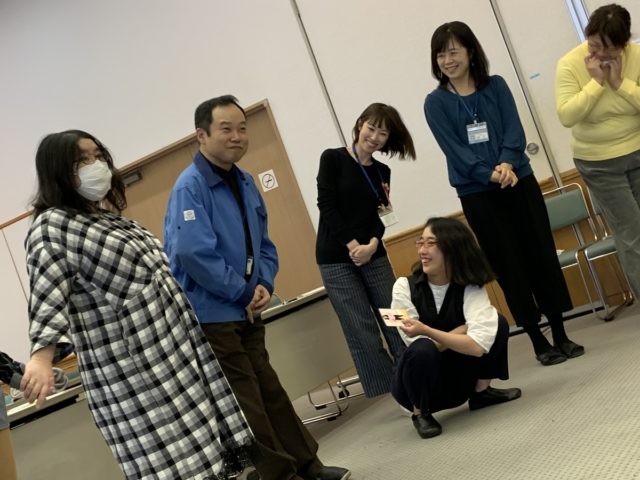明日2月11日(火)東久留米で第5期演劇ワークショップの記録映画『ほらクマ学校を卒業した三人』と『Secret of Pukapuka』の上映をします。
第5期演劇ワークショップには栃木から毎回新幹線に乗って参加した方がいました。中学生の息子さんが「新聞を読んで感想を書こう」という宿題に取り組んでいるときにたまたま朝日新聞に載った「障害者と一緒 豊かな生」という記事を見つけ、それがきっかけで親子で参加することになりました。
お母さんの方は、最後の反省会の時、ぷかぷかさんといっしょにやったワークショップが楽しくて楽しくて…と話ながら号泣してしまいました。号泣するほどの関係がぷかぷかさん達との間にあったのです。どうしてそんな関係が生まれたのか、お母さんと息子さんの感想を紹介します。
●お母さんの感想から
みんなすごく素直で思ったことをストレートに表現するから、リアルで人間味があってとても魅力的に思えて、私はぷかぷかさんの大ファンになっていました。私にとってそこは自然と笑顔になれる場所で、優しい空間でした。そんな彼女、彼たちと一緒に立った舞台。やり切った感、ハンパなかった。ぷかぷかさんたち一人ひとりとふれあった思い出が頭の中で駆け巡り、みんなで頑張った喜びと終わってしまった寂しさとが複雑にからみあって、涙がこぼれ落ちてしまいました。本番直前、廊下の片隅でセノーさんと手を繋ぎ練習したときのあのいい表情も脳裏に焼き付いて離れません。



私が最後に泣き崩れてしまったとき、ボルトくんが背中を支えに来てくれました。彼はずっと大丈夫?と声をかけてくれていました。私が落ち着くのを待って手をはなそうとする時も「もう手をはなしても大丈夫かな?」「放すよ、いいかな?」って言って自分の席にもどられました。今まで生きてきてこんなに優しい言葉をかけてもらったことがあったかいなと、やさしさが心に響いて本当に癒されました。彼のやさしさに心から“ありがとう”と言いたいです。誰かと心で繋がれることって何よりも力になる。私も人の喜びや悲しみにそっと寄り添えることができる人間になりたいと思います。
●息子さんの感想から
中学二年生の夏休み。「相模原殺傷事件」が起きた。「障害者は生きる価値がない」と。あまりの衝撃に朝起きて顔も洗わず、テレビのニュースにしがみついていたのをよく覚えている。
僕は被告のような思想は誰の心にもあるのではないかって、それがずっと心の奥で引っかかってきた。例えば街で障害者の方が突然大きな声を出す様子に嫌悪感を抱き、関わりたくないと思ってきた自分。中学生になり、知的障害者施設にボランティアに行こう!と誘われたときに、障害者の方は怖いという勝手な思い込みで、「行きたくない。それだけは勘弁して」と言い張った自分。それは僕も無意識に差別する側に立ち回っていて、被告の発想と心の奥底で繋がっているのではないかと。僕の心は弱くて醜い。“やっぱ俺は、クズだな・・・”と思ってずっと過ごしてきた。
一年後の夏休み、“新聞を読んで感想を書こう”という宿題のため新聞の記事を探していたら、〝障害者と一緒 豊かな生″という見出しに目が留まった。ぷかぷかパン屋さんの記事だった。僕はなぜかその記事を捨てずに取っていた。高校生になったある日、たまたま付けたテレビ番組にぷかぷかさんや高崎さんがでていてあの新聞記事とリンクしたことに少し驚いた。母からワークショップに誘われたときは、どうしようか悩んだが、高崎さんのいう豊かになるってなんだろう、それが知りたくて確かめたいと思った。

(2017年7月25日朝日新聞)
ぷかぷかさんと接してきておもしろかったり、ときにはむっとしてしまったり、いろいろあったけれど、何よりも僕は人前で表現するとかが嫌で嫌で、そこから逃げていた自分だったように思う。リハーサルの日もそう。僕にも役があり、しかもオオカミのかぶりものまであるとわかったとき、やっぱり今日は部活にいっておけばよかったなと後悔した。舞台に立つなんてなれないことに身体はどっと疲れた。しかし、ぷかぷかさんたちはニコニコ元気、とてもいい笑顔だった。疲れた顔をしているのは僕だけで「なんでこの人たち笑っていられるんだろう」と不思議だった。その姿を見ていて、ぷかぷかさんたちはやらされてるとかでなくて、自由にありのままの姿で表現することを楽しんでいる。特に一緒にオオカミ役をやったしょうくん(こうきくん)が♪なんでもいいから一番になーれ♪と歌っている姿がきらきらと輝いてとっても印象的だった。僕にはやらされているという気持ちがずっとどこかにあった。ぷかぷかさんと僕の違いはそういう心の違いだと思った。


本番当日。舞台も終わり、最後に円陣を組んでみんなの意見を聞いていたとき、しょうくんが泣きながら、この演劇に対しての思いを話しているのを聞いて、心にぐっと突き刺さるものがあった。僕の前で悪ふざけしたり、おどけてみせるしょうくんしかみえていなかったので、あんなしっかりした思いで頑張ってきたんだと、それに比べ僕はなんなんだ。本番はでたくないと、なんか駄々をこねている小学生のようだったと恥ずかしくて穴があったらはいりたくなった。そして、元気の出ない僕に「着替えよう」とか「頑張ろう」と声をかけ続けてくれたしょうくんや、相手を思いやり大切にするぷかぷかさんたちの姿をみて、生きる価値がないなんてとんでもないぞ。なんて生きる価値のある人たちだろうと思った。

一緒に参加した母はこの半年、本当に楽しそうだった。最後に母が泣いているのを見たとき、この人はぷかぷかさんたちと心と心で向き合って同じ気持ちを感じてきたんだなと思った。
来年は部活を頑張ろうと思う。でも、いつか大学生とか社会人になって、また改めて参加してみたい。そのときは母に負けないように心の底から楽しみたいと思う。高崎さんのいう何が豊かになるのか今の僕にはまだわからないけれど、恥ずかしくてたまらんかった舞台に、ぷかぷかさんたちと一緒に立ててよかったと今、思っている。ありがとうございました。

しょうくんへ
僕なんかと一緒にオオカミ、やりにくかったよね。ごめんなさい。そしてありがとう。
いつかまたしょうくんと一緒に豚でも馬でもなんでも、タッグを組んでやりたいです。

演劇ワークショップという場は、こんな素晴らしい関係を作ってしまうチカラがあります。明日上映する映画には、そのチカラがいっぱい写っています。ぜひ見に来て下さい。
やまゆり園事件の公判が続いています。先日も書きましたが、事件であらわになった問題は、被告を裁いてすむことではありません。やっぱり私たち自身が障がいのある人たちとどんな風におつきあいし、どんな風にこの時代を一緒に生きていくのか、ということが問われていると思います。
その問いに対するひとつの答えが、明日上映する映画にはあります。
いつも言うことですが「支援」とか「なにかやってあげる」という上から目線の関係では、こういったものは生まれません。ではどうしたらいいのか、そのヒントが映画にはあります。