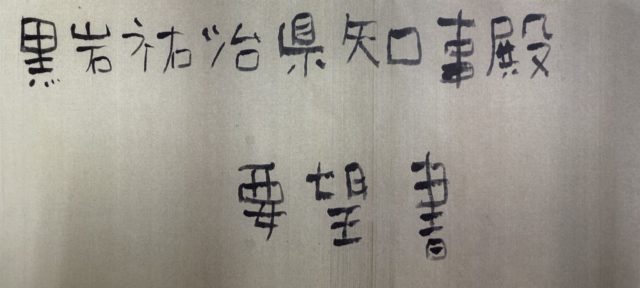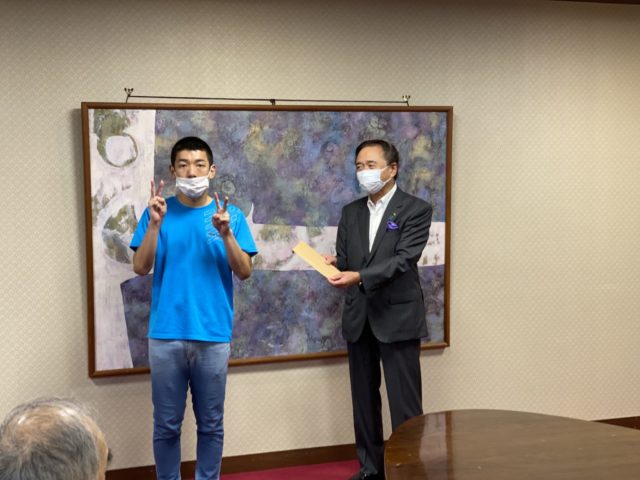障害者施設における虐待問題の記事です。
●虐待の要因を「問題行動を抑える技術にしか考えが及ばず、利用者にふさわしい支援を行うという基本的な理念が不足していた」と指摘。
問題行動があるから支援が必要、と考え、その支援の中身が暴力でしかないのが虐待。利用者さんが重度障害者であれば、その虐待を訴えることもできません。そばにいる人が気づくしかないと思います。やまゆり園では13時間も拘束された女性がいたようですが(2年前のNHKスペシャル)、にもかかわらず誰も「それはおかしい」と指摘する人がいなかったのは、誰が考えても異常な環境です。
暴力に対する感覚が麻痺しています。相手が人であることを忘れてしまっています。だから暴力を振るうことに何の抵抗もないのだと思います。
「支援」という上から目線の関係は、相手と人としてつきあう、ということを阻害するのではないかと思います。そういう観点からの検証こそ必要な気がします。
「基本的な理念が不足していた」という指摘は当たっていますが、そういう理屈っぽい話以前に、利用者さんたちと人として出会ってなかったことこそ、いちばんの問題だと思います。
●「事件が障害者施設の職員によって起こされたという事実をわれわれ入所施設の管理者は重く受け止める必要がある。法人は自らの支援を見直すべきだし、第三者による検証も必要だ」
やまゆり園は、事件はすべて植松死刑囚のせいにし、自らの支援の中身を見直すことは一切しませんでした。だからこそ、事件後も虐待が続いているのだと思います。こんな法人に支援施設を任せていいのかと思います。
そもそも、あれだけの事件を起こしながら運営を続けていること自体がおかしいと思います。仮にぷかぷかであのような事件が起こったら、多分ぷかぷかはやっていけません。どうしてやまゆり園はやっていけるのか。監督責任者の神奈川県は、どうして許すのか、説明すべきだと思います。