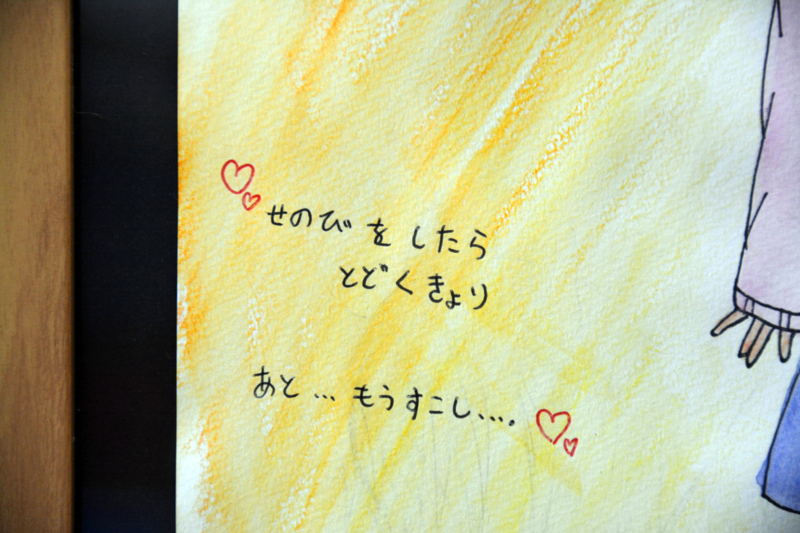昨年やった「表現の市場」を見に来た人たちの感想を載せるのを忘れていました。今年は9月からワークショップをスタートさせ、来年2月14日(日)に「表現の市場」をやります。場所はみどりアートパークホールです。
・全員が一生懸命やっていてよかったです。涙が出ました。
・ちょっと見て帰ろうと思ったのですが、おもしろくて、楽しくて席が立てなくなりました。今日の舞台を見てたくさんの人たちが「おもしろい」「楽しい」と思うようになったら、世の中、もう少し生きやすくなると思います。
・みなさん一生懸命取り組んでいて、感動しました。ダンスでは車いすの方が立ち上がって踊り出し、胸が熱くなりました。
・笑顔いっぱいの表現力は素敵でした。
・涙が出ました。ありがとう!
・また家族で見に来たいと思いました。
・表現することを楽しまれ、見ている私もうれしくなりました。今後もこの活動を続けていって欲しいです。
・大変おもしろかった。みなさんすごい出来でした。ありがとう。
・様々な表現がすばらしかったです。
・楽しませていただき、ありがとうございます。みなさまの努力が心に残ります。
・楽しかった。感動しました。
・みなさん、生き生きと表現されていて、すばらしかったです。また来てみたいと思いました。楽しい時間をありがとうございました。
・とてもすばらしい内容で、楽しく拝見させていただきました。今後ともこの市場が長く続くことを楽しみにしております。
・素敵な企画をありがとうございました。
・第1部から第3部まで大変すばらしかったです。どのパフォーマンスも、とっても元気をもらえました。誰もが明るく、明日を生きていこうと思える演技でした。次回も楽しみにしています。
・とてもすばらしい演劇でした。
・どのグループも精一杯さが伝わる演技でした。デフパペットさんはすばらしかったです。
・とっても楽しくて笑いがいっぱいのステージでした。自由に表現する出演者のみなさんを見ていたらいっしょにやりたくなりました。第2回、第3回と続いて行くといいなと思います。
・みんな明るくて、とてもよかった。どんどん発展して欲しい。
・みなさん、レベルが高く、驚きました。元気と笑顔をもらいました。
・多くの人に見て欲しいです。
・みんな頑張って、キラキラしていました。
・こういうことができる街はすばらしいと思う。
・みなさんの努力、表現力、すばらしい!
・デフパペットシアターのすばらしい表現力に魅せられました。
・心あたたまる演目ばかりで、すごくよかったです。
・心から楽しませていただきました。今後がとても楽しみです。
・まさに表現の市場でした。どの舞台も、障がいのあるなしに関わらず、それぞれの人が一生懸命舞台に立っている姿に感動しました。ありがとうございました。
・よかったです。また見せていただきたいです。
・心がほっこりしました。演劇としてとか、メッセージとか関係なく、みんなといるだけで、そのままで、なんだか癒やされる感じがしました。
・「森は生きている」を見に来ました。地域の人たちといっしょに作っている雰囲気がとてもよかったです。感動して涙が出ました。
・テキトー版「赤ずきん」超おもしろかった。ぷかぷかの「森は生きている」超おもしろかった。たくさん練習したのですね。すばらしかったです。
・とてもおもしろかったです。自由でありながら、全体としてステージが成立しており、ユーモアにあふれ、いい時間でした。個性と多様性あふれるパフォーマンスに、こちらも元気になりました。他者への壁(バリア)が少ない彼らの存在に、現代社会が学ぶことも多いなと思いました。
・みなさんのパワーあふれるパフォーマンスに心打たれました。みんなの楽しそうな笑顔が最高でした。それぞれのすばらしい表現に感動しました。
・照明、音楽、演出、小道具、とっても垢抜けていました。
・どのグループの発表もすばらしかったです。ぜひ続けていただきたいです。みなさんはいろいろ可能性を持っていることをあらためて感じさせていただきました。
・どれもすばらしかったです。来てよかったです。