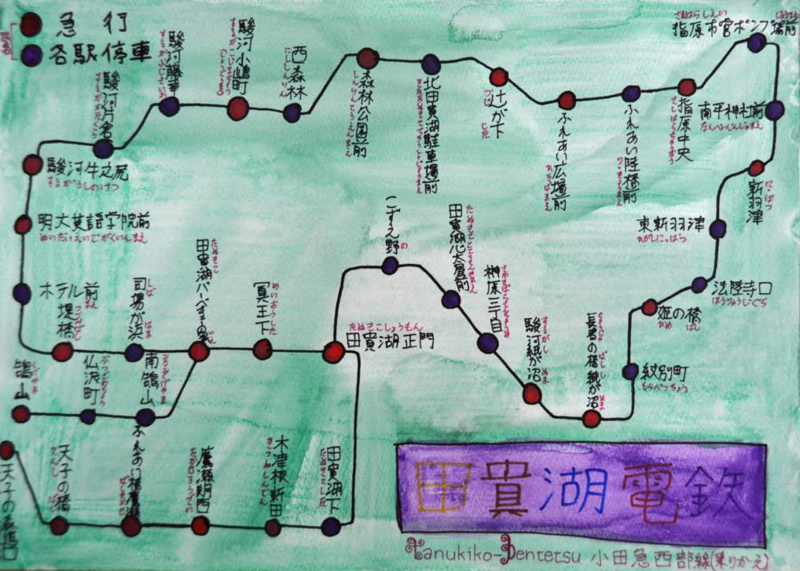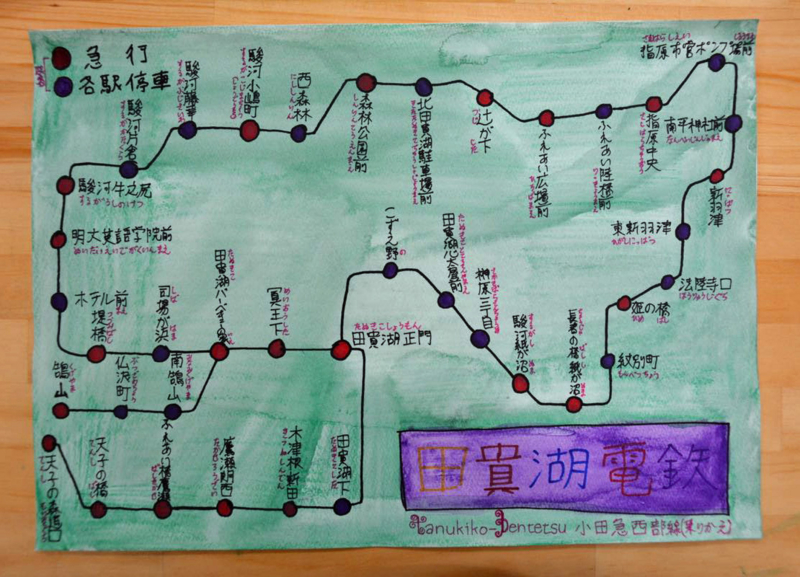一昨日載せた《「障害者」って言葉は、何だか違う》という記事を読んだ、辻さんのお母さんからこんなメールが来ました。
《 最新のぷかぷか日記を読ませていただき、感動しました。
こんなにも克博たちと真剣に向き合って下さる方達がいるなんて!
親は否応なく克博たちの世界の一員になりますが、パン教室に来てくださっている方達は積極的に関わってくださっています。凄い!
私に関していえば恥ずかしながら何十年も克博の出来ないことをできるようにしよう、何とか社会に迷惑をかけないようにしよう、と見当違いの努力をしてきました。率直にいって、それが学校や作業所から求められてきたことだからです。
でもぷかぷかでの克博の働きぶりを見て、考え方が変わりました。
そして、今、軽々と今まで私が考えていた越えがたい違いを超えていこう、という機運が感じられます。
親からしたら感謝の念しかありません。
これからも地域で克博が、ぷかぷかの皆が地域の一員として自然に、楽しく生きていけたらな、と思います。》
なんかうれしいですね。ぷかぷかがやってきたことが、保護者の方からこんなふうに評価されるなんて。
「できないことをできるようにしよう」「社会に迷惑をかけないようにしよう」と「見当違いの努力をしてきました」、それは「学校や作業所から求められてきたことだから」
障がいのある人たちはもちろん、その保護者の方も多くは、こんなふうに縮こまって生きてきたんだな、と今更ながら思いました。
もっともっと自分らしく、お互い堂々と生きていけばいいと思うのです。ぷかぷかは素直に自分を差し出している利用者さんたちに支えられています。それがぷかぷかの魅力になっています。
先日、利用者さんの出勤しない日があって、パン屋に来たお客さんが、
「あら、なんかすごく静かで、さびしいわね、ぷかぷかじゃないみたい」
とおっしゃっていましたが、彼らのためにと思って始めたお店が、いつの間にか、彼らに支えられる、彼らが主人公のお店になっていました。彼らがいない「ぷかぷか」は、もう想像できないくらいです。
彼らがいなければ、ただのパン屋で、お客さんはただパンを買って帰るだけ。今の「ぷかぷか」を思うと、なんだかとても淋しい気がします。
うるさいほどににぎやかで、元気があって、よくわからないおしゃべりが飛び交って、つい、クスッと笑ってしまったり、心がキュンとあたたかくなったり、パンを買うだけでなく、何かあたたかいお土産をいっしょに持って帰るような、そんなお店になっています。
いろいろ理屈をこねたり、苦労したりではなく、「彼らと一緒に生きていきたい」とただそのことだけを考えてやってきたら、こんなお店になっていた、というだけです。特別なことは何一つせず、普通に、楽しく、日々やってきただけなのに、知らないうちに、保護者の方に「見当違いの努力をしてきました」と思わせるくらいの「新しい価値」を生み出していた、というところが、おもしろいなと思うのです。

ツジさんは、ほとんど一日中レジのそばで、こうやって手を上げてぶつぶつおしゃべりしながら、お客さんが買ったパンの値段はレジよりも速く暗算で計算します。なんとも不思議な人です。
そのツジさんを見つめる子どもの目がいい。世の中にはこんなお兄さんもいるんだよ。ずっとおしゃべりしてるけど、よーく聞くとすごいことしゃべってるんだよ。計算もすごい早いし、20年前の紅白歌合戦の出場歌手を全部言えたりするんだよ。こういう人と仲良くすると、いいことがいっぱいあるんだよ。