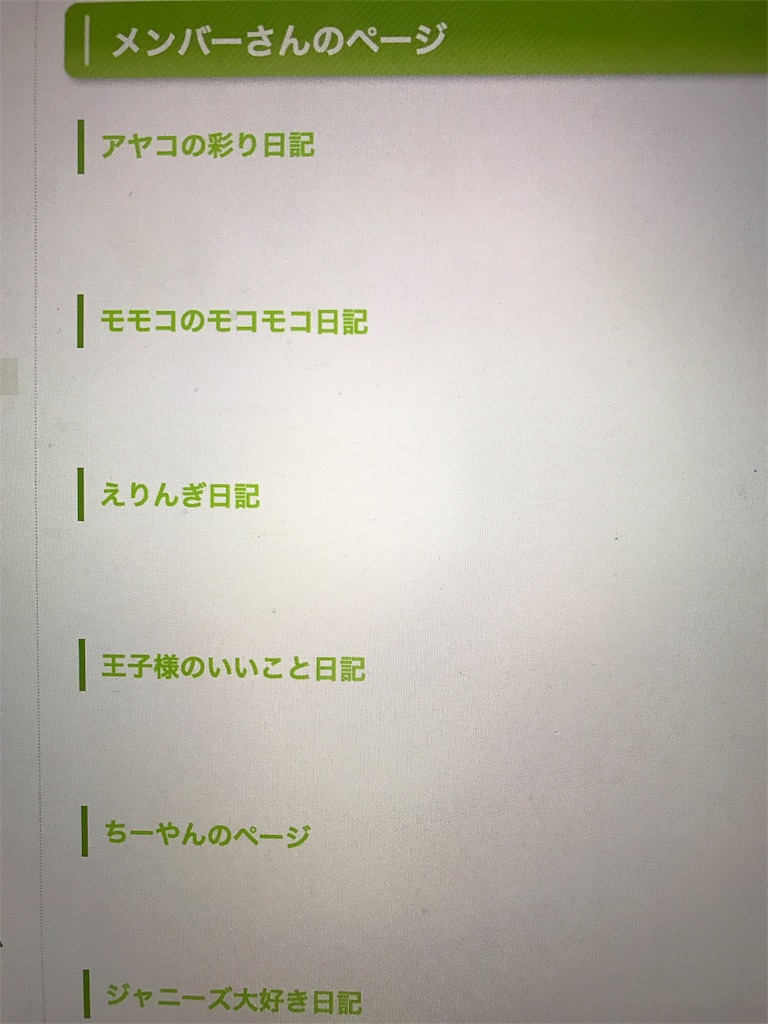昨夜は瀬谷区の二ツ橋大学であった相模原障害者殺傷事件の犠牲者の追悼集会に行ってきました。
津久井やまゆり園で犠牲になられた方々への追悼の集い
いろんな方が発言され、とてもいい勉強になりました。
事件の容疑者は精神障害の人かと思っていましたが、福祉新聞の記者福田さんは、「措置入院までに精神科にかかったことがなかった」「措置入院の終わったあとの外来診察では主治医は「躁鬱病は考えにくい」と診断」「生活保護の申請の際、面接したケースワーカーさんも精神を病んでいるとは思わなかった」といったあたりを考えると、精神を病んだ人が犯した犯罪とみるのはおかしいのではないか、と報告され、目から鱗が落ちる思いでした。
措置入院のことがやたら話題になっていますが、容疑者が精神を病んでいたわけではない、となると話が全くちがってきます。論点がずれ、大事な問題が見えなくなっていくような気がしました。
30年ほど前、瀬谷にある生活クラブのお店の駐車所で「あおぞら市」というのがあり、そこに養護学校の生徒たちと地域の人たちで一緒に手打ちうどんのお店を出しました。そのときに手伝いに来ていた人が容疑者の闇の部分が私にもあります、と発言していました。
《 高崎さんに声をかけられて手伝いに行ったものの、障害のある人たちにどう接していいかわからずほんとうに困りました。「ああ、うう」とかしかいえなくて、よだれを垂らしながら歩き回っている人がいて、正直気持ち悪くて、私の方へ来なければいいなと思っていました。ところがお昼になってご飯を食べるとき、たまたまテーブルがその子とお母さんが座っているテーブルしかあいてなくて、ここでやめるのも失礼かと思い、勇気をふるってそこへ座りました。そのとき、そのよだれを垂らしている子どもが私に向かって手を伸ばしてきました。ああ、困った、と思いながらも拒否するわけにもいかず、思い切って、本当に思いきってその子の手を握りました。
すると、その子の手が柔らかくて、あたたかいんですね。もう、びっくりしました。なんだ、私と同じじゃないかと思いました。この発見は私の中にあった大きなものをひっくり返した気がしました。
その子のやわらかくて、あたたかい手にふれるまで、その子をモノとしか見てなかったのです。容疑者とおんなじだと思いました。でもその子の手が、その闇から私を救い出してくれた気がしています。》
いいお話しだと思いました。こうやって人と人が出会い、そこから新しい世界が始まっていくように思いました。
結局のところ、こうやって障害のある人たちと出会う機会がないことが、相模原障害者殺傷事件を生むような社会を作っているように思います。
会場になった「せやまる」のすぐそばにある三ツ境養護学校に子どもの頃よく遊びに行った人がいて、その方の話によれば、昔は塀もなく、自由に学校に入り込んで一緒に遊んでいたそうです。それがいつの間にか高い塀がたち、全く中には入れなくなったといいます。こうやって彼らと社会を分ける方向に世の中は進んできたのだと思います。
あおぞら市での手打ちうどん屋の試みは、そんな社会にあって、地域の人たちと障害のある人たちの出会いのきっかけを作ろうとしたのでした。お手伝いに来た人はほんとうにいい体験をしたと思います。
お手伝いに来た人の話を聞きながら、「あ、ケンタローだ」とすぐに思い出しました。「ああ、うう」とかしかいわず、よだれを垂らしながら歩いていました。気に入った人がいると手を伸ばしてきます。養護学校の教員になって2年目に担任した生徒で、彼と過ごした楽しい日々はその後の私の生き方を決めた気がしています。
ケンタローは犬が好きでした。私も好きなので、ある日散歩の途中で犬を見つけ、二人で駆け寄りました。私は普通になでなでしたのですが、ケンタローはがばっと抱きしめ、びっくりした犬の顔をぺろぺろなめはじめたのです。私はなんだか感動してしまいました。「犬が好き」というのはこういうことなんだと、ぺろぺろ犬の顔をなめているケンタローから教わった気がしています。
そのケンタローのかわいい手が、うどん屋のお手伝いに来た人を救ったのだと思うと、ケンタローもえらいな、と思いました。