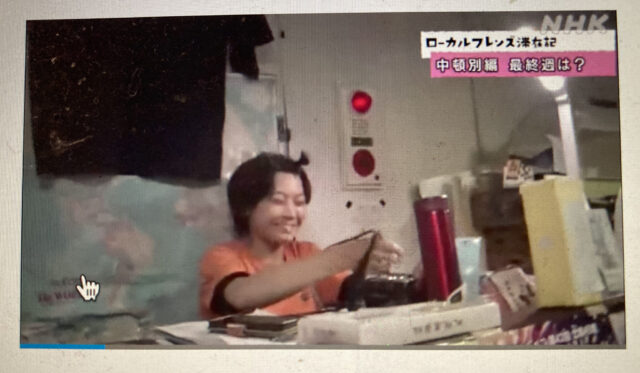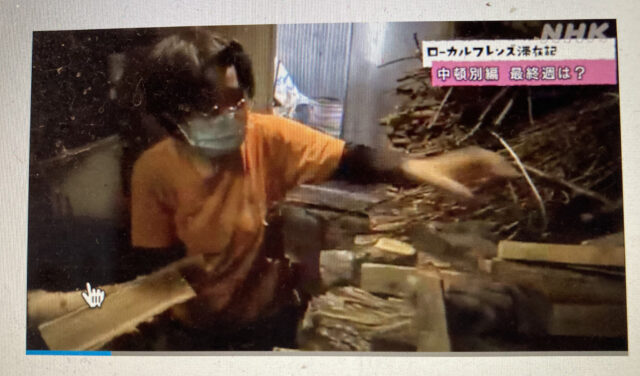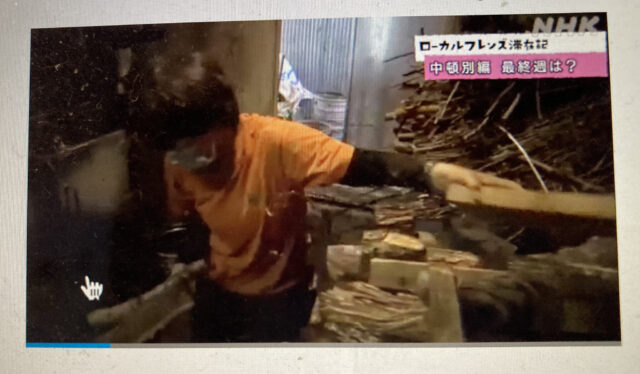津久井やまゆり園事件から7年目、事件に関する話が飛び交っていますが、大きな話を語っても、社会はなかなか変わりません。それよりも身近にいる障がいのある人達と日々楽しい物語を作り、それをまわりに人に伝えること。それによって
「彼らとはいっしょに生きていった方がいいね」
って思う人を少しずつ増やすこと。それが事件を超える社会を作ることにつながっていくと思うのです。
●日々の暮らしの中でクスッと笑える小さな物語を作り続ける
「やる気スイッチ」のシャツを着た人がいました。スイッチをピッと押すと、こんな顔になりました。私もやる気がない時、このシャツを着て、誰かにスイッチをピッと押してもらおうと思いました。

こんな風に堂々と寝てる人がいました。私はこんな風には寝られないので、こんな生き方をうらやましいと思いました。彼らを支援するとかじゃなくて、彼らの生き方を素直にうらやましいと思うこの感覚こそ大事な気がします。

なんで写真撮るんだよ、という人がいたので、
「美男、美女がそろっているのでつい写真撮っちゃいました」
っていうと、女性たち
「美女って、私たちのことだよね」
なんて話していて、なんて素直なんだ、としみじみ思いましたね。愛おしき人達です。

●ぷかぷかの映画見て、わいわい、がやがや、すったもんだ
映画見たあと、映画を見ての気づきを元に「障がいのある人たちといっしょに生きるって、ほんまにトク?」をテーマに、みんなでわいわい、がやがや、すったもんだ議論しましょう。こういう議論はとても大事。こういうことが社会を前に進めます。
●ぷかぷかが作ってきた物語を集めた『ぷかぷかな物語』はおすすめ
事件で排除された障がいのある人たちといっしょに生きることで生まれた物語。彼らは不幸しか生まない、と事件の犯人は言いましたが、彼らとの日々は私たちの心をほっこりあたためてくれます。事件を超える社会を作るヒントがいっぱいです。

この本を読んだ人の感想
●「障がい児」の親たちだけでなく、今、子育て真っ最中だったり、思春期と格闘したり、介護に悩む人たちにも、この本を薦めたい。
面倒くさくて、ムカムカ腹がたって、厄介な相手にカッカッとしながらも、ふと気づく「可笑しさ」。そんな気づきから、「へぇ~、オモロイ奴やなぁ」って思えるようになるのかも?
この本の魅力は、何よりも「肩に力が入っていない」ところ。
いやもちろん、著者が「カフェベーカリーぷかぷか」を立ち上げるまでの並々ならぬ奮闘ぶりには圧倒されるばかり。簡単に起ち上げたわけではない。
それでも、著者の筆致は軽やかでユーモアがあり、私は一緒にハラハラしたり、ホッとしたり、ニマッと笑ったり・・・。どんどん、肩の力が抜けていくのを実感する。
それにしても、巷でよく見聞きする「障害者支援」・・・そんな「上から目線の」お堅い言葉を蹴散らしていく著者のフットワークの軽さ、いつのまにか周囲の人を巻き込んでしまうエネルギーの源は何なのだろう?
一般には「大変だ」とか「厄介な」「可哀想な」などと形容されてばかりの障がいを持つ人たち。そんな彼らに「ひとりの“人”として」体当たりで向き合う、その中で、彼らの「可笑しさ」「おもしろさ」に気づく著者の温かな視線。「凄い」と目を丸くする柔らかな心。・・・これこそが、著者のエネルギーの源だと思う。
「こうした方がいい」「こうすべきだ」といった議論や説教ではなく、「へぇ~、おもしろい」「スゴイじゃん」・・・こんな言葉が、人を励まし、勇気づけ、背中を押す。
そんな魔法が「ぷかぷか」にあるから、「ぷかぷかさん」たちは、あんなに元気で、生き生きしていて、うるさくて、面倒で、・・・でも、愛おしい。
●ぷかぷかを知った時、私は息子たちの為にぷかぷかの秘密を知りたいと思いました。でも、ぷかぷかを知るほどに私自身の生き方を考えるようになってきました。
●私も障害のある子どもを育てていますが、家族になってよかった。家族があたたかくなりました。ぷかぷかさんは社会をあたたかくします。耕します。
●この本はある障害者就労継続支援事業所B型のお話ですが、同じくB型で働いている私としては全く違った視点で事業展開されていることに大きく関心をもちました。
まず感じたことは障がいをもつ人たちを支援する対象とした見方でなく、「共にはたらく・生きる」同志として地域を巻き込み(耕す)ながら一緒に活動し、そのほうが絶対楽しいということ。そして持続性があること。「多様性を認め合うインクルーシブ社会の実現を」とどこでも耳にしますが、今の社会の在り方は、教育、就労が障がいをもつ人たちとそうでない人たちとを分けた制度の上で成り立っています。
分離が進むほどその社会の規範に縛られて、障がいをもつ人たちがその多様性を認めてもらうどころか社会に合わせるために押し殺さなければならない、ますます支援、配慮の対象にされてしまう。
ぷかぷかさんのように障がいをありのまま楽しむ方法を作り上げれば、そこに生産性も生まれ、制度も使い倒し、地域も社会も豊かにしていくことを実現していけるのだなととても参考になりました。
何より、ぷかぷかさんたちがとても魅力的です。
●我が家にもぷかぷかな息子たちがいます。彼らといっしょに生きていると、私自身も、みんなもいっしょに幸せになれるんだと気づかせてくれます。
●障がいのある子ども達に惚れ込んで、一緒にいたくて作ったのが「ぷかぷか」。
だから、内容もおもしろくてあったかくてやさしい。
「好き」という思いで、まわりを巻き込んで、心を耕してやわらかくする。その場も街も、ふかふかにしていく。「あなたが好き」から出発した世界に人間の上下はない。
人を矯正していく支援はやはり無意識に「上下」があるのだと思う。相手だけでなく、修正する側も自分自身が縛られていく。自分を修正し、社会も修正しようとする。
それが今の息苦しさにつながっているのではないだろうか。
●本の表紙に引寄せられました。綺麗な色使いにちょっと不思議な動物達。
すらすらと短い時間で読めて分かりやすく、読み終えると不思議に何だか心の角がとれて、軽くなる誰かに話したくなる一冊。
様々な場面で登場するぷかぷかさん達にパワーを充電して貰えました。高崎さんの思いつきはやはりただ者ではなさそうですね。
●よくある「福祉事業所」とは程遠い世界の成り立ちや世界観に引き込まれてしまいます。「障がいがあっても、社会に合わせるのではなく、ありのままの自分で働く」「障がいの無い人も、障がいのある人と一緒に生きていったほうが幸せ」
この本に出逢い、いてもたっても居られなくなり、実際に「ぷかぷかさんのお店」にも行ってきました。本の通りの明るく楽しく元気なお店で、とても幸せな時間を過ごせました。
●障がいのある子ども達に惚れ込んで、一緒にいたくて作ったのが「ぷかぷか」。
だから、内容もおもしろくてあったかくてやさしい。
「好き」という思いで、まわりを巻き込んで、心を耕してやわらかくする。その場も街も、ふかふかにしていく。「あなたが好き」から出発した世界に人間の上下はない。
人を矯正していく支援はやはり無意識に「上下」があるのだと思う。相手だけでなく、修正する側も自分自身が縛られていく。自分を修正し、社会も修正しようとする。
それが今の息苦しさにつながっているのではないだろうか。
●今日は1日あたたかかったけど、本を読んで最高にあたたかい気持ちになりました。ぷかぷかさんは、存在そのものが、やさしい。この本を持って、みんなにサインしてもらいに行かなきゃ。おいしいぷかぷかのパンが売り切れちゃう前に。ほんとにみんな、大好きだよー
●『とがった心が丸くなる』もおすすめ
養護学校の教員をやっていた頃書いた本。障がいのある子どもたちと一緒に過ごすと、こんな楽しい物語が生まれます。事件の犯人は、障がいのある人達とこんな楽しい時間を過ごしたことがなかったのではないかと思います。

養護学校のプレイルームに突如出現した『芝居小屋』。役者もお客もくったくたになって一緒に芝居を作る。障がいのある子どもたちがいてこそできた、みんなが自由になれる空間。『海賊ジェイク』がゴンゴン進む。

アマゾンで販売中
www.amazon.co.jp
アマゾンKindle会員であればただで読めます。
この本を読んだ人の感想
ぷかぷかのお店に来ていただければ、元の本『街角のパフォーマンス』(オンデマンド版)もあります。