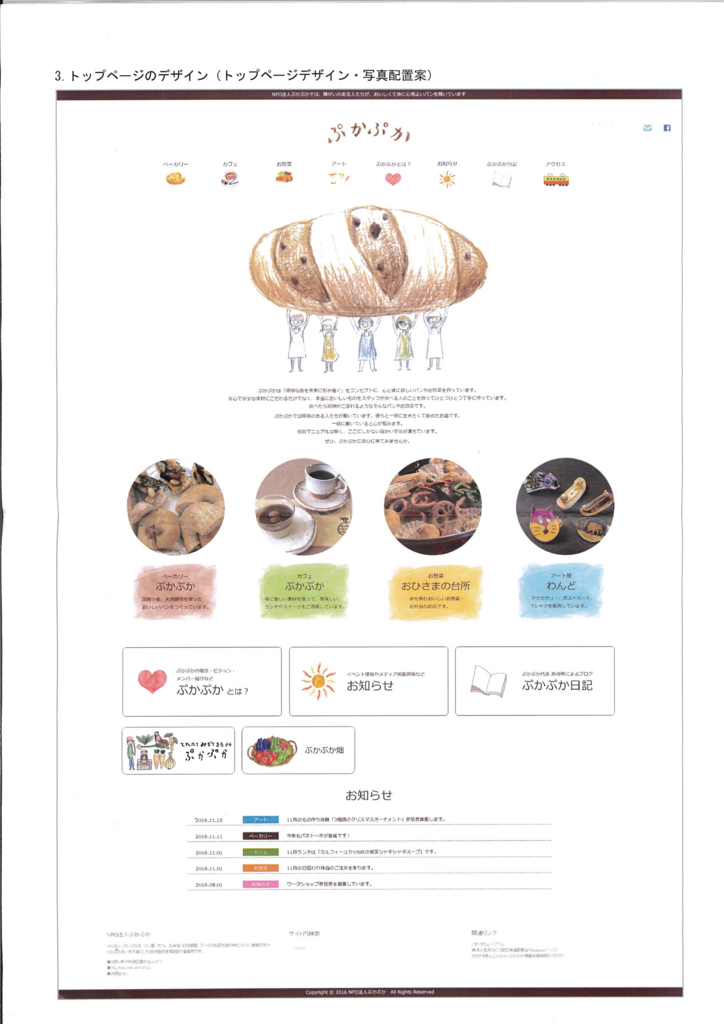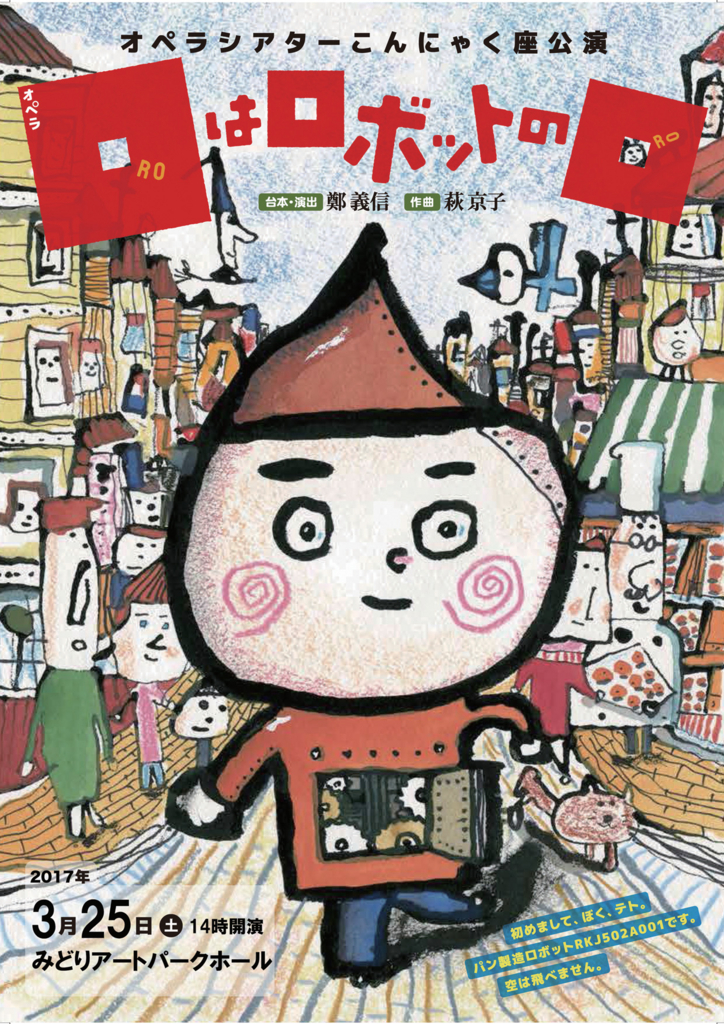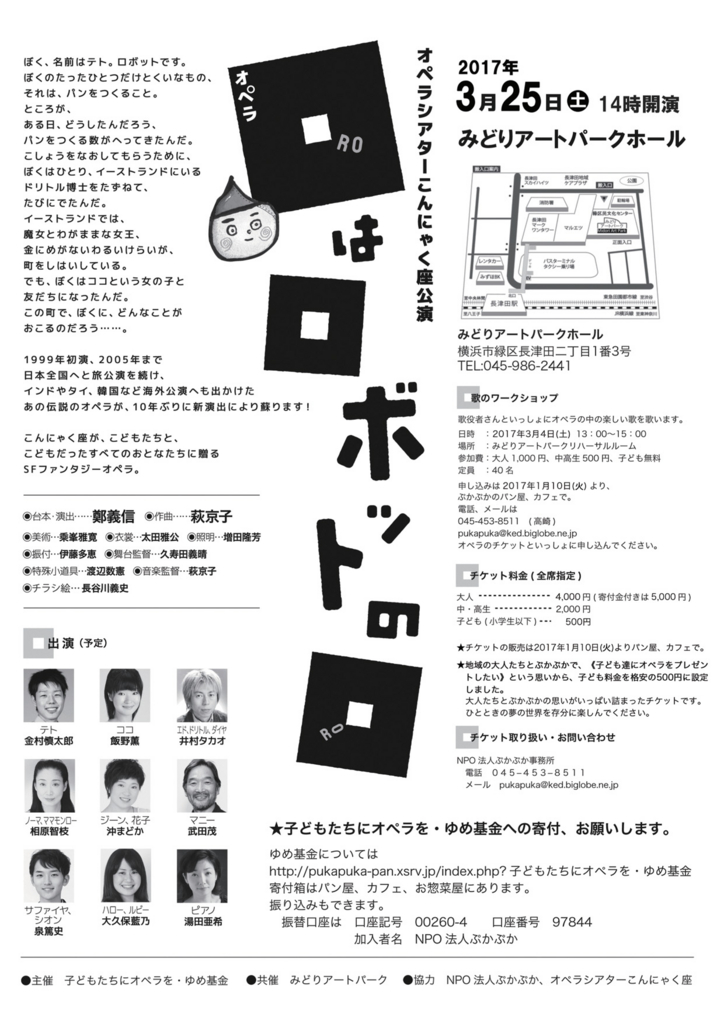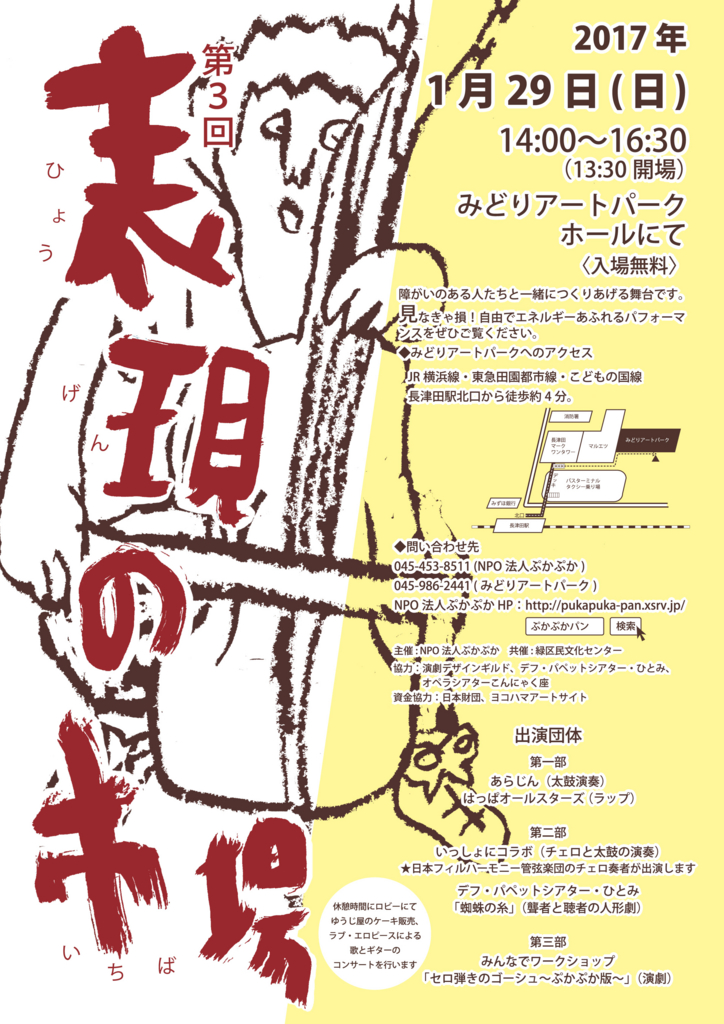福祉事業所でパンを作っているおじさんがパンの研修にきました。57才のとても気さくなおじさんです。話しぶりからして、利用者さんと一緒にパンを作ることが楽しくて楽しくてしょうがない、といった雰囲気でした。利用者さんを指導するとか支援する、といったことが大嫌いで、そうなったら、仕事に行くことがつまらなくなるじゃないですか、とおっしゃっていました。理屈ではなく、感覚的にそういうものはいや、という感じです。利用者さんと楽しく働く関係を壊したくない、という気持ちが強いのだと思います。「支援員」と書いた名札が嫌でねぇ、なんてお話しもされていました。
利用者さんと毎日楽しくやっていると、若い常勤職員から、「そんなに甘やかさないで下さい」とか「きちんと指導して下さい」といわれたこともあり、ゲンナリしたそうです。でも、ま、そういうことをきちんとやっていれば、福祉事業所の中で出世?して、私くらいの年であれば施設長くらいはやっているのですが、利用者さんに対して指導とか支援といった関わりはなんかつまらない気がして、結局は職場を転々とすることになった、とおっしゃっていました。ずっとパートの立場で贅沢はできませんが、毎日利用者さんと楽しく仕事をする、というのがいちばん幸せなことです、とおじさんは目を細めて語っていました。
こういうおじさんのおかげで、福祉事業所の現場が楽しくなっているのだろうと思います。おじさんをぷかぷかにつれてきた保護者の話だと、利用者さんの間では「ジャムおじさん」と慕われ、超人気者だそうです。職場の風景が目に浮かぶようです。
おじさんも利用者さんと一緒に働くのが大好きで、利用者さんも「ジャムおじさん」と働くのが楽しみで、これこそが「障がいのある人たちと一緒に生きること」なのだと思います。
お互い一緒に働くことが楽しいと思える職場こそがいちばんです。指導だの、支援が大事、とスタッフが考えている限り、職場はお互いつまらないものになります。
指導とか支援しか考えられないのは、利用者さんたちと「人として出会っていない」のだと思います。人として出会っていれば、ジャムおじさんのように、彼らと一緒に働くこと自体が楽しくなります。それがないから「指導」とか「支援」という関係に、自分がそこにいる理由を求めるのだと思います。そのことが「一緒に働く職場」をつまらないものにしていることにいい加減気づくべきだと思います。
ぷかぷかでは毎日帰りの会で「いい一日でしたか?」という質問をします。毎日はかけがえのない一日です。それをいい一日とするか、つまらない一日とするのか、とても大事なことだと思います。指導とか支援は、利用者さんのかけがえのない一日をだめにしてしまっているんじゃないか、そんなふうに思います。
以前にも書きましたが、養護学校の教員をやっているとき、毎日のようにフリチンで芝生の上で大の字に寝っ転がって、ニカニカしながらおひさまを仰いでいる子どもがいました。私はそばで「パンツはきなさい」と陰気な顔をして言い続けていました。でも、こういうことを毎日続けていると、ひょっとして彼の方がいい時間を過ごしているんじゃないか、とだんだん思い始めました。ニカニカしながらおひさまを仰いで気持ちよさそうにしている子どもと、陰気な顔をしてグチグチ言っている私とどっちがいい時間を過ごしているか、ということです。そのことに気がついてから、もうグチグチつまらないことをいうのはやめて、その子と一緒に大の字になって寝っ転がってひなたぼっこをすることにしました。
いい時間を過ごすこと、いい一日を過ごすこと、そしてそれを何よりも大事にすることは、そのフリチン少年に教わった気がします。人生のとても大事なことを教わったと今でも思っています。それが帰りの会の「いい一日でしたか?」につながっています。はじめの頃は手を上げる人はほとんどいませんでしたが、だんだん質問の意味をわかってもらえて、今では何人もの人が手を上げて、私のいい一日を発表してくれます。
ジャムおじさんは毎日そんないい一日を利用者さんと作っているんだろうなと思います。