ぷかぷか日記
タカサキ日記
オペラ『ロはロボットのロ』をまたやります。

この夏、子どもたちに本物のオペラをプレゼントしようと思っています。オペラシアターこんにゃく座のオペラ『ロはロボットのロ』という、すばらしく楽しいオペラです。このオペラ、子どもたちに大好評で、今回で3回目の公演です。 ドキドキ、わくわくが止まらない、恋と冒険の物語。 子どもたちにオペラをプレゼントする,というのは、おもちゃやお菓子をプレゼントするのとは、全く意味合いが違います。オペラはひとときの夢の世界です。それを子どもたちにプレゼントするというのは、何かこう、企画自体に夢があるというか、わくわくします。 ひとときの夢の世界を子どもたちに楽しんで欲しい。それをすると何かが変わるとか、何かリターンがある,というわけではありません。ほんのひととき、夢の世界を子どもたちが、思いっきり笑顔で楽しむ、ただそれだけです。ただそれだけのために、子どもの好きな大人たちで汗をかきたい。そういう企画です。 オペラ『ロはロボットのロ』は1ステージ80万円ものお金がかかります。わずか2時間ちょっとの、ひとときの夢の世界を80万円で買うのです。そして「さぁ、思いっきり楽しんで」って子どもたちにプレゼントするのです。 たくさんの、とびっきりの笑顔が見られます。 上演後、歌役者さんたちと握手、握手 魔女は子どもたちに大人気 子どもたちにひとときの夢の世界をプレゼントしたい方、子どもたちのために汗をかきたい方、募集します。詳しくは後日ぷかぷかのホームページで発表します。
詩に命が宿った感覚になった

ぷかぷかの近くの東洋英和女学院大学でぷかぷかさんとの出会いを「みんなの詩 」にまとめ、それを朗読するワークショップをやりました。「みんなの詩」を作った日に、とりあえずそれを朗読しましたが、今回はもう少し丁寧に朗読しました。 前回は立ったままで読みましたが、今回は歩きながら読んでみたり、座ってみたり、読むときに表情を作ったり、声のトーンを変えてみたりしました。そのことで、詩の印象がどんな風に変わるか確かめてもらいました。 そうやって、言葉に丁寧にふれる、という体験をしました。それはとりもなおさず、ぷかぷかさんとの出会いを、いつもとはちがう方法で振り返ることになります。 詩は丁寧に朗読することで、読み手と聞き手の間で、むくむくと生き始めます。みんなの体験が、生きた言葉として、人に伝わるのです。 授業が終わったあとの感想に 《 詩に命が宿った感覚になった。》 というのがありましたが、むくむくと生き始めた言葉をしっかり受け止めたのですね。 「共生教育論」という、福祉の授業です。その中で、こんなにも深い言葉が出てきたこと、それがすばらしかったと思います。 ぷかぷかさんたちとの出会いを、朗読の中ではっきりと追体験した人たちもいました。 《 ぷかぷかさんと出会う前はみんなよいイメージを持っていなかったから、声のトーンを低くしたり、座って読んだりしました。出会ってからは彼らのよい面にたくさんふれられて、明るいイメージになったことをうまく体と声のトーン、表情で表現できたと思います。 私がよいなと思ったのは「いっしょに笑うこと」という文では、みんな目を合わせて笑顔になったり、手を繋いでみたりして読んだことです。》 ぷかぷかさんたちの自由さに、自分たちが助けられていたことに気がついた人もいました。 《 大勢の中で演技することはとても恥ずかしくて、照れくさかったです。ぷかぷかさんたちがいれば、恥ずかしさが少し消えるなーと感じました。》 いずれにしても、ぷかぷかさんとの出会いが、学生さんたちにこんなにも豊かな時間をプレゼントした気がしています。それぞれが体験したことを詩に書き、それをみんなの詩としてまとめ、更にそれを思いを込めて朗読する。すべてぷかぷかさんとの素敵な出会いが出発点です。その出会いがなければ、こんなにも豊かな時間を学生さんたちが持つことはなかったと思います。 障がいのある人たちとの関係を、こんなふうに豊かなものに変えていく試みを、もっともっとあちこちでやった方がいいと思います。 みんなの詩 第Ⅰグループ ぷかぷかさんと 出会う前 分かり合えるか不安だった どのように接していくか 最初は心配だった はじめは不安だった 何をするか分からない 未知の世界だった 緊張とワクワク どのように接したらいいか はじめは分からなかった 近寄りがたかった そんな彼らが怖かったけど 手をつないだ時 印象が180度変わった 温かさ 伝わってきた 言わば奇跡 互いを理解しようと努力した 出会いとは偶然ではなく 出会いとは必然 出会ってみると 触れることで あたたかい気持ちになって ハイタッチ効果 予測不可能だからこそ わくわくした すごく自由な人たちだった 仲間になった 人と関わる 楽しさを知った 楽しいと思える瞬間があった 彼らはおもしろい ぷかぷかさんと出会えて よかった 出会いに感謝 第Ⅱグループ 出会う前は どこか避けている自分だった 障害者は怖かった 相手にしたくなかった 不安でいっぱいだった どんな人が来るか とても緊張していた でも ぷかぷかさんに出会って それは変わった 自分らしく 自由な心で 素直な生き方 ありのままの姿 優しい方ばかりで 知らないことを知って 理解して 考えてみた よりよい世の中とは 一緒に笑うこと 楽しく過ごす 関わってみて 心が穏やかになった 元気付けられた ぷかぷかさんと接して 楽しかった 楽しい気持ちになれた お互いのことを もっと知りたくなった 教えたくなった 思い出ができた 自由で様々 みんないい 第Ⅲグループ 最初はこわかった 出会ったことでなくしてくれた 近づきづらい イメージがあった 壁のようなものを感ずるが 分かり合えた 出会う前は むずかしそう 最初は不安だった 近づきたくなかった 出会ってすぐのハイタッチ 「よろしくね」「仲良くしよう」 怖いとかじゃない 身近になった ぷかぷかの人との出会いが 楽しい時間 人との関わりの中で 知らなかったことが 思い出せた日々 我々にないポジティブな世界 ただただ自由なんだ かざらなくてよい とても素直な笑顔がたくさん 生まれるものは 「素直」ということ たくさんの優しさ ぷかぷか浮く 空にある雲みたい 全ての人が 繋がる世界へ
たかが直感、されど直感

先日、福岡でやったワークショップに参加した方の感想です。ぷかぷかに対するこんな評価いただいたのは初めてです。あらためてぷかぷかが創り出してきた新しい価値を思いました。 indigohorizon.info 私は戦略を立てて事業を進めてきたわけではなく、「気色悪い」に代表される直感や思いつきでぷかぷかを作ってきました。今のぷかぷかの雰囲気は、この「気色悪い」という直感から始まったといっていいと思います。たかが直感、されど直感なのです。 障がいのある人たちが自分らしく働ける場を作ろう、といって始まったわけではないのです。そういう正しい、美しい思いでは、多分今の泥臭いぷかぷかはできなかっただろうと思います。 そもそも私には福祉を始めよう、という思いは全くありませんでした。どこまでも惚れ込んだ彼らといっしょに生きていきたい、そのための場を作ろう、という思いだけでやってきました。だからこそ、今までの福祉では語れないようなおもしろい場ができたのだと思います。 最近関わり始めたぷかぷかの近くにある東洋英和女学院大学では石渡先生のやっている「共生教育論」で5コマもらい、私の授業をやりました。石渡先生は福祉の業界ではとても有名な方で、相模原障がい者殺傷事件で神奈川県の事件検証委員会の委員長を務めた方です。そんな先生の授業を受けている学生さんたちが、私の授業を受け、ぷかぷかさんたちと出会い、ぐんぐん変わってきました。 授業のあと、自分の人生を振り返るような感想がたくさん出てきました。今まで石渡さんがやってこられた従来の福祉の授業では、多分出てこなかった感想です。私を語るような感想です。 学生さんの変わりように、石渡先生がびっくりし、最初3回の授業予定が5回まで伸び、とにかく自由にやらせてもらいました。 最後の2回はぷかぷかさんとの出会いを詩に書き、それをみんなの詩としてまとめ、それをお互いの前で朗読しました。こんなことは従来の福祉の授業では絶対にやりません。 最後の朗読の授業のあと、「劇団四季の気分で楽しかった」と感想を書いた学生さんがいました。授業の中で「自分を開く」あるいは「自由になる」ような体験をしたのだと思います。 ぷかぷかさんとの出会いは、そんな風に人を自由にするものを持っているのだと思います。それを授業の中で実感できたのだと思います。 障がいのある人たちは、人を自由にするチカラを持っている、ということです。 授業の名前は「共生教育論」でした。学生さんたちは、いっしょに生きていった方がトク!ということを学んだと思います。この学びが今後どんな風に発展していくのか、楽しみなところです。
ほんまにうまくできるんか、とはらはらしながら…

第五期演劇ワークショップの6回目。 青い目のミツバチたちの踊りを作るためにプロのダンサー伊藤多恵さんに来てもらいました。 www.jafra.or.jp ほらくま学校の「なんでもいいからいちばんになれ」の目標にみんな振り回されている社会にあって、青い目をしたミツバチたちは全くマイペースで日々を送っています。 赤い手の長い蜘蛛と、銀色のナメクジ、顔を洗ったことのない狸がそろってほらくま学校を卒業し、謝恩会などをやりながらも、腹の中ではお互い 「へん、あいつらに何ができるもんか、これから誰たれがいちばん大きくえらくなるか見てゐろ」 と思っていました。かたくりの花の咲く春です。 《ちゃうどそのときはかたくりの花の咲くころで、たくさんのたくさんの眼の碧あをい蜂はちの仲間が、日光のなかをぶんぶんぶんぶん飛び交ひながら、一つ一つの小さな桃いろの花に挨拶あいさつして蜜みつや香料を貰もらったり、そのお礼に黄金きんいろをした円い花粉をほかの花のところへ運んでやったり、あるいは新らしい木の芽からいらなくなった蝋らふを集めて六角形の巣を築いたりもういそがしくにぎやかな春の入口になってゐました。》 赤い手の長い蜘蛛が、なんとか一番になろうとがんばってがんばって巣をどんどん広げ、えさをとりまくり、ため込みすぎたえさがどろどろに腐って、蜘蛛もいっしょに腐って地面に落ちてしまいます。つめくさの花の咲く夏です。 《ちゃうどそのときはつめくさの花のさくころで、あの眼の碧あをい蜂はちの群は野原ぢゅうをもうあちこちにちらばって一つ一つの小さなぼんぼりのやうな花から火でももらふやうにして蜜みつを集めて居りました。》 銀色のナメクジは、やってきたかたつむりをとトカゲを相撲で投げ飛ばしたり、うまいこといって食べてしまいます。ぐんぐん大きくなって、カエルが来たときも相撲で投げ飛ばすのですが、塩をまかれ、溶けてしまいます。蕎麦の花が咲く秋でした。 《さうさうこのときは丁度秋に蒔まいた蕎麦そばの花がいちめん白く咲き出したときであの眼の碧あをいすがるの群はその四っ角な畑いっぱいうすあかい幹の間をくぐったり花のついたちひさな枝をぶらんこのやうにゆすぶったりしながら今年の終りの蜜みつをせっせと集めて居りました。》 顔を洗ったことのない狸は「山猫大明神様の思し召しじゃ」とか、うまいこといってウサギとオオカミを食べてしまいます。オオカミが持ってきたもみの袋も食べてしまい、そのもみがおなかの中でどんどん育ち、おなかが破裂します。冬の始まりの頃でした。 《このときはもう冬のはじまりであの眼の碧あをい蜂はちの群はもうみんなめいめいの蝋らふでこさへた六角形の巣にはひって次の春の夢を見ながらしづかに睡ねむって居りました。》 この、春、夏、秋、冬の場面のミツバチたちの踊りを考えました。 伊藤さんは季節ごとのちょっとしたエピソードを拾い上げ、一人一人から表現を引き出していきます。 たとえば春の場面で 《日光のなかをぶんぶんぶんぶん飛び交ひながら…》の「ぶんぶん」はどうする? 《一つ一つの小さな桃いろの花に挨拶あいさつして蜜みつや香料を貰もらったり》の「もらったり」波動する? と、みんなに聞き、アクションで返してもらいます。そのアクションを今度はみんなでやります。そういったことを繰り返しながら、その場面での振り付けをどんどん作っていきます。わずか2時間足らずで春、夏、秋、冬の場面の振り付けを作ってしまいました。 この振り付けにチェロとピアノが入ります。チェロは日本フィルハーモニーの江原さん、ピアノはオペラシアターこんにゃく座の湯田さんです。春、夏、秋、冬を同じ楽譜でイメージを変えて即興で演奏してくれました。 www.youtube.com 花岡さんの感想です。 久々にダンスなるものをやりました。 講師の振り付けをひたすら覚えるダンスしか経験なかったので、 ブンブンはどうする? もらうはどうする? あげるはどうする? とみんなで考えた振りをつなげてダンスにしてしまう流れがとっても楽しかったです。 面白い振りを考えるのには、結構自信がありましたが、 二見さんの振り付けが、もう天才的に面白く、どう頑張っても、逆立ちしてもマネできないレベルでとっても悔しかったです笑 ●● 金沢から参加した菊池さんは ダンスつくるプロセス。あんなに自由にそれぞれの内から出てくる動きをつなぎ合わせて。 個人から出た動きをみんなの動きに変化させるマジックみたいでした。 ●● 今回初参加のMiyanoさんは ダンス、とにかく楽しかったです。もともとダンスには苦手なのですが、ひたすら楽しくできました。うまくやらなきゃ、とかいいとこ見せなきゃ、という気持ちを持たずにできたからかと思います。それもやはり、ミツバチチームボルトさん、いくちゃん、さらにななちゃんのおかげです。全力で取り組んでいたので、私もただ全力で楽しむことができたんだと思います。朝、ゆみっちさんに会ったとき、ずっとやってたいくらい楽しいよと言われたのですが、本当にそうでした。 他のチームも、1人ひとりの存在がすごい・・。 改めて、表現するってどうゆうことか、考えてしまいました。 あまりに楽しかったので、来週のワークショップも参加できるように調整しております。 ●● 蜘蛛の場面はデフパペットシアターひとみの人たちとの影絵とのコラボになります。 子どもの蜘蛛たち 怪しい山猫大明神のお祓いの練習 ダンスの打ち合わせ ちょっと休憩 音楽ディレクター藤木さんと 金沢から参加した菊池さんの感想です。 ●● 今回で2回目の参加でしたが、 練習回数が残り少ないをわかっていたので、ちょっとした焦りも漂う雰囲気を感じていました。 自分らしさというか、お茶目さなのか。それぞれなぷかぷかさん達をみていて、本番を経験したことのない私は、正直 「このままでいいの?!」 というきもち… それでも、ワークショップが終わる頃には失敗とか成功ではなくて、今、この場に様々な人がいることが、まず素晴らしいことなんだ。 と思いました。 ずっと近くにいて、お昼ゴハンも一緒に食べようと誘ってくれたぷかぷかさんと関わる中で、ぷかぷかさん達だけじゃなく、参加しているみんなや観てくれる人でつくるのが 「表現の市場」なのかもしれない。 “私たちが共に在るという表現” それは、ぷかぷかさん達と一緒じゃないと完成しないよなぁ。 と思います。 …そうだとしても、何十人という多様な人を一緒にステージに立たせようとする高崎さんたちのパワーを感じずにはいられませんでした。 ●● 26日にもう一回ワークショップをやり、27日午前中舞台でリハーサル、午後本番です。ほんまにうまくできるんか、とはらはらしながら先へ進めるこの時期が一番楽しいです。 27日「表現の市場」で発表します。 n
NHKラジオ深夜便

2016年12月16日にNHKラジオ深夜便で放送した「明日への言葉《障害者の力をビジネスに》」が1月25日午前1時台に再放送される予定でしたが、先日『世界の旅』で有名な兼高かおるさんが亡くなり、以前インタビューしたものを25日、26日に放送することになり、ぷかぷかの話の再放送はなくなったという連絡が入りました。別の日に再放送するようにディレクターの方から強くプッシュするそうですが、それがかなうかどうか、今の時点ではわかりません。もし再放送が決まればまたお知らせします。 とりあえずテキスト版がありますので、興味のある方はご覧下さい。 pukapuka-pan.hatenablog.com
その場に立つ、という体験

「障がいのある人と働く意味を考える」をテーマに、福岡でワークショップをやってきました。 中央官庁で障害者雇用数を水増しした、などという恥ずかしい事件が話題になっています。一番の問題は、障害者雇用率のみ押しつけられ、どうして障害者を雇用するのか、という理由が語られてないところにあります。今年度中に4000人新たに障害者を雇用する、とありましたが、ただただ障害者雇用率だけを達成すればいい、という意図が見え見えで、一番大事なところが抜け落ちています。どうして障害者を雇用するのか、という議論です。それは社会の中で、障がいのある人たちといっしょに生きる意味を考えることであり、そういう議論こそが社会を豊かにします。そこを避けてしまう社会は、何かすごくソンしてる気がします。 そんな中で「障がいのある人と働く意味を考える」という福岡からの提案は、障害者雇用の問題を現場目線で考えよう、という、今までにない提案でした。障害者雇用、というとどうしても雇用する側の発想になるのですが、それを一緒に働くことになる現場の人の感覚で考えてみよう、ということでした。それをワークショップという手法を使って考えよう、というわけです。 机に座っての議論と何がちがうのか。 簡単な芝居を作って、それを演ずるので、実際に当事者になって、そこから世界を見る、という体験ができます。 机に座っての議論は、あーだこーだと言葉のやりとりに終始することが多いのですが、ワークショップは実際にその場に立つ、その場を生きる、感じる、そしてそれを表現するということが大きいと思います。今までにない気づきがそこにはあります。 感想の中に「芝居の中で当事者になることで、より具体的に想像できました。」「障がいのある方といっしょの働く同僚を演じて、かける言葉に悩みました。」と言った言葉がありましたが、机に座っての議論では絶対に見つからない気づきです。 その気づきこそ、新しい価値観を生み出す可能性を持っているように思うのです。 業界のCSR情報誌で「障害者雇用」を特集したとき、編集している社長さんが、生産性の論理ではない、新しい価値観を生み出さないと、「障害者雇用」はうまくいかない、と書いていましたが、ワークショップの中での気づきは、その可能性を秘めていると思っています。 今回の企画は、 ・障がいのある人たちと一緒に働く人の立場で考える。 ・ワークショップの手法を使って、実際にその場に立ち、その場を生きる、感じる、考える、そして表現する。 という二つの新しい試みでした。 時間が短かったので、そういったことが十分にやりきれたとは思えないのですが、それでも参加した人たちにとっては、すごく新鮮な体験だったようです。まずは最初の一歩です。ここから新しい価値創造に向けて、動き出すのだと思います。 smilemika.com
以前出演したラジオ深夜便が再放送

NHKラジオ深夜便のディレクターからうれしい連絡が入りました。2016年12月16日に放送した「“障がい者の力”をビジネスに」が今月25日〈金〉の午前1時台に再放送されることになりました、と。もちろんこれは予定であって、いろんな都合で動く可能性もあります。そのときはまたFacebookなどでお知らせします。 NHKの中で高い評価があったからこその再放送だと思います。障がいのある人たちのチカラを見直していこう、という動きが、こんなふうに出てくることはすばらしいことだと思います。 ぜひ聞いて下さい。 www4.nhk.or.jp
「支援」という関係から自由になる
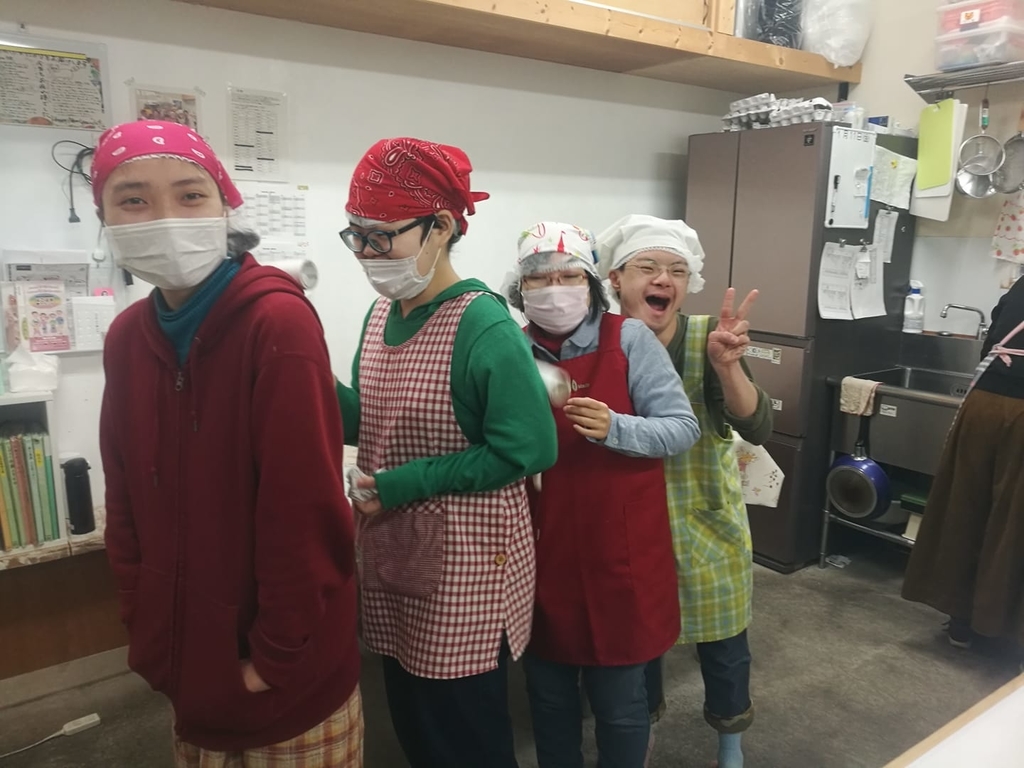
福祉事業所で働く人たちの集まりで上映会と私の話をしました。映画も話もとても興味を持って聞いてくれました。話を聞くときの集中の度合いがすごかったですね。 映画の中で笑顔が多いことにみんなびっくりしているようでした。この反応は、一般の上映会ではなかなか見られないことです。ということは福祉の世界ではこういう笑顔がなかなか見られないのかもしれません。 「こんな笑顔にするにはどうしたらいいですか?」 というストレートな質問も出ました。 みんなが笑顔でいるのは、いろんな要素があると思うのですが、とりあえず三つくらいあげました。 ①仕事が楽しいこと、 ②彼らのありのままの姿で働けること ③フラットな関係であること ①はほかのお店に負けないくらいおいしいパン、お惣菜、お弁当を作っています。「障がいのある人が作ったから買ってあげる」という関係ではなく、「おいしいから買う」という関係こそ大事にしています。その関係を維持するために、日々おいしいものを作る努力をしています。 区役所でほかの事業所と弁当販売の日が重なったことがありました。「じゃあ、お互い競争すれば、もっとおいしいものができるんじゃないの」と私は考えたのですが、相手は「いや、うちは福祉だから競争しません」などといいました。 本気でいいものを作ろうという気持ちがないのだと思いました。それを「福祉」という言葉でごまかしている。 いいものを作ろう、という気持ちがなければ、いいものは生まれません。いいものが生まれなければ、売り上げも伸びず、職場の活気も生まれません。当然、笑顔も生まれません。 笑顔は「職場の活気」を表現する一番のバロメーターだと思います。 「うちは福祉だから競争しません」」という言葉は、仕事をする場として、何かとても大事なものをはじめから放棄しているように思います。 福祉の世界も、もっとビジネスに力を入れるべきだと思います。いい商品を作り、それが売れれば、仕事が楽しくなります。みんなの仕事のモチベーションが上がります。みんなの笑顔が自然に増えます。笑顔が増えるとお客さんも増え、更に売り上げが増える、という好循環が生まれます。 ②障がいがあってもなくても、自分らしく働けること、それは笑顔の一番の源泉です。 「障がいのある人たちは社会に合わせなければいけない」という社会の圧力の強い中で、彼らのありのままの姿ををどこまで大事にできるか、です。私自身は社会に無理に合わせようとするぷかぷかさんたちの姿が気色悪かったので、社会に合わせることをやめました。社会の圧力を押し返すような大事な決断をするとき、自分らしく働くことを大事にしよう、といった美しい理念だけでは負けてしまいます。「気色悪い!」といった泥臭い感覚の方が、こういうときはかえって強い気がします。結果的には、「ああ気色悪、もうだめ!」というところで出てきた決断をたくさんのお客さんが支えてくれました。そのままの姿で働くぷかぷかさんが好き!と。これは全くの想定外でした。 ③障がいのある人たちと私たちはどこまでフラットな関係を築けるか、は私たちの生き方が問われる問題だと思います。彼らの前に、どのように立つのか、ということです。上から目線で立つのか、それともフラットな目線で、フラットな関係で立つのか。 立たれる側から考えれば、上から目線で目の前に立たれると、あんまりいい気分ではありません。笑顔になれる気分ではありません。相手がフラットな目線であれば、それは仲間の一人であり、当然笑顔でおつきあいします。 彼らとフラットな関係を築いて何が一番いいかというと、彼らと新しいものをいっしょに生み出すクリエイティブな関係になるからです。創造する喜びをいっしょに分かち合うことができます。表現の市場の舞台は、その創造する喜びが満ちあふれていると思います。 ぷかぷかのお店も、パンやお惣菜、お弁当だけでなく、毎日新しい価値をいっしょに創り出しています。 「障がいのある人たちは地域を耕し、地域を豊かにしている」というのはぷかぷかのお店が創り出した今までにない新しい価値です。パン、お惣菜、お弁当だけでなく、文化という面でもクリエイティブな活動をやっているのです。 今回の集まりで気になったのは、何かにつけ「支援」という言葉が出てくることです。障がいのある人たちと「支援」の関係にあることから、なかなか自由になれないのだと思いました。「支援」という関係にいる限り、フラットという関係はあり得ないし、クリエイティブな関係もあり得ません。目の前に素敵な人たちがいるのに、クリエイティブな関係が切り結べないなんて、もったいない話だと思います。その気になれば1+1=5くらいの価値が生まれるのに、1+1=1にとどまってしまうのは、実にもったいないです。 1月8日のブログに 映画『Secret of Pukapuka』の中で、近所のオーヤさんが、 「前はぷかぷかさんを上から目線で見てたかもしれないけど、ぷかぷかさんとおつきあいするようになってから、自分の方がえらいと思わなくなりました」 というようなことをおっしゃってますが、まさにこの感覚です。フラットな関係はここから生まれます。誰かに言われてやるのではなく、自分からそのことに気がつくこと。 福祉事業所の人たちも、そのことに気がつくとき、ようやく「支援」という関係から自由になるのだと思います。もっともっと楽しいことをいっしょにやることです。心の底からいっしょに笑う、ただそれだけです。
現場の人が納得し、前向きになるような障がい者雇用の理由を自分たちで探す

昨年暮れに朝日新聞で報道された記事です。 digital.asahi.com 障がい者雇用率を達成するために1019年末までに4,000人もの障がい者を雇用するそうです。 こういうのを発表する人はいいのですが、4,000人を実際に受け入れる現場の人たちは大変だろうなと思います。 障がい者雇用に関しての一番の問題はここにあると思います。障がい者雇用率達成の部分だけが押しつけられ、どうして障がい者を雇用するのか、雇用すると現場はどうなるのか、といった現場の人たちが前向きになる言葉がどこにも見当たらないのです。 朝日新聞は 「障がい者雇用への意識が低かった」 などと書いていましたが、それを書くなら、厚生労働省に障がい者を雇用する理由をきちんと書くべきではないのか、といった提案こそすべきです。実際に障がい者を受け入れることになる現場の人が納得し、前向きになるような障がい者雇用の理由です。 これを現場目線で先取りしちゃおう、というのが1月14日(月)福岡で開かれるワークショップです。 pukapuka-pan.hatenablog.com 生産性の論理を超えるような新しい価値を、障がいのある人たちと一緒に働く中にどこまで見いだせるかが、大きなポイントになると思います。 全日本印刷工業組合連合会が発行しているCSR情報誌で障がい者雇用を特集したとき、ぷかぷかしんぶんに載せた「生産性のない人が社会に必要な理由」という記事が転載されたことがあります。 pukapuka-pan.hatenablog.com この情報誌の編集をやっている社長さんが全国から10人ほど、2月19日(火)ぷかぷかに研修に来ます。 障害者 雇用はもはや福祉の文脈で語るのではなく、 企業の「戦力」として活用できるか、その人 材活用のノウハウを持つことができるかどう かという人材戦略の文脈で語るべきであろう。 「生産性」だけの議論に陥ることなく、視野を 広げ、多様な人材がそれぞれの個性を活かし て活躍できる場を創造していくことは、日本 が世界をリードする真の先進国として発展し ていくことにもつながっていくだろう。 といったことを書くようなすごい社長さんたちが集まります。すごく楽しみです。 いずれにしても、私たちの側から、障がいのある人たちと一緒に働く理由をもっともっと見つけ出していく必要を感じます。
「どうしてぷかぷかに来るとホッとするんだろうね」 の問いは、新しい一歩
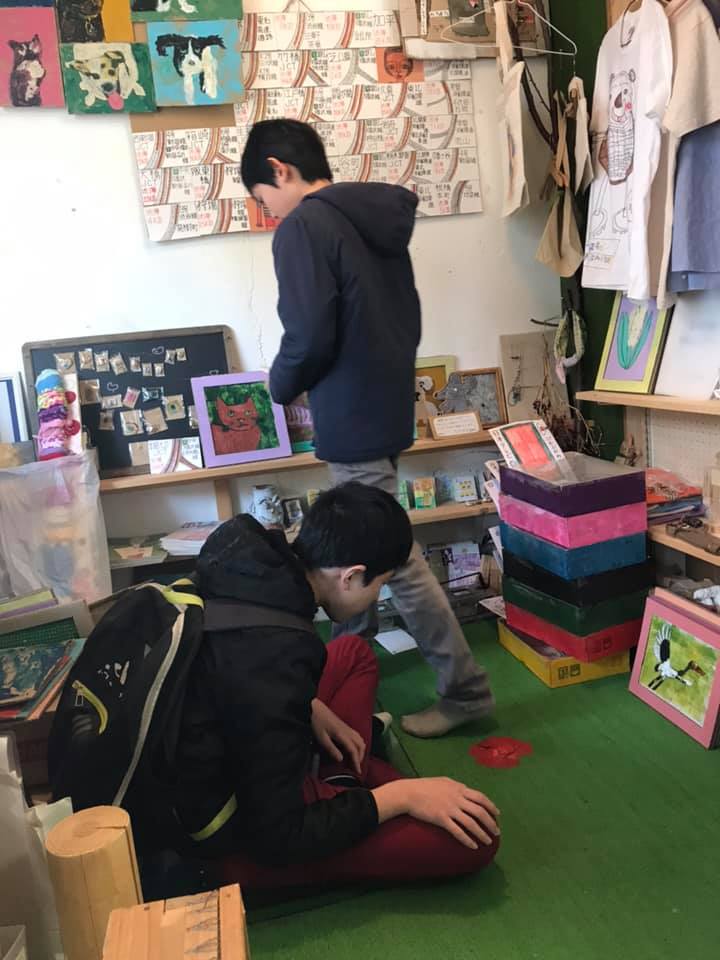
「うちのぷかぷかさん」がぷかぷかに遊びに来ました。浅川そら君とたから君です。 ameblo.jp ぷかぷかには障がいのある方たちがたくさん見学に来ます。たいていは保護者の方、区役所のケースワーカーさん、施設の職員の方と一緒で、それなりによそ行きの雰囲気で見学します。みんなお行儀がいいのです。 そら君、たから君はいつものそら君、たから君だったようです(ようです、と書くのは、残念なことに私は体調を崩し、その日は休んでいたからです)。別にお行儀が悪い、というわけではなく、ふだんから自由に生きているんだろうなぁ、と思えるような振る舞いだったようですね。 わんどはごちゃっとしていて宝物の山みたいなところですから、二人とも大喜びで宝物探しをやったようです。普通なら、「あ、そこはさわらないで」とか、いろいろ注意したりするのですが、ぷかぷかはそういうことを一切しません。特にそう決めたわけでもなく、なんとなく、ま、楽しんでもらえばいいか、ぐらいの気持ちで見ています。 大事なものがないわけではありません。商品製作途中のもの、演劇ワークショップで使う小道具、大道具など、大事なものはいっぱいあります。みんな壊れたら困るものばかりです。それでも「あ、そこはさわらないで」みたいなことはいいません。 違ったのはそれを安心して見ていられる 私だけだったかもしれません。 とお母さんが書いていますが、ふだんは安心して見ていられない場面がいっぱいあるのだろうな、と思います。安心して見ていられない、というのは、彼らの自由な振る舞いを認めない社会がある、ということです。そこは多分、私たち自身も不自由な社会です。だからぷかぷかに来ると 「ホッとする」 とみんないいます。 本当は、 「どうしてぷかぷかに来るとホッとするんだろうね」 と、自分に問い、その問いを抱えながら社会を見ていくことが必要なんだろうと思います。何が問題なんだろう、どうしたらいいんだろう、と考える。ここがすごく大事だと思います。 「ぷかぷか、よかったね」 で終わらせないことが大事です。 「どうしてぷかぷかに来るとホッとするんだろうね」 の問いは、新しい一歩になります。新しい物語の始まりになります。
ぷかぷかトピックス
障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。








