ぷかぷか日記
タカサキ日記
4万円からはじまった物語

区役所の区政推進課の職員Kさんが、異動になりますと挨拶に来ました。Kさんは採用1年目でぷかぷかを相手に仕事をやったので、ま、いろいろ大変だったようです。 区政推進課とのおつきあいは、地場の野菜を使う地産地消を通した関係でした。Kさんが来たときも秋の区民まつりでぷかぷかのおからを出す費用の打ち合わせでした。おからの費用が6万円で、区役所が用意している予算が10万円でした。差し引き4万円が残ります。それはもったいないと、その4万円で地産地消ブースのデザインをやらせてくれませんか、とその場の思いつきで提案しました。この時の思いつきが、アートを通したおつきあいの始まりでした。 突然の提案でKさんも係長も即答はできず、区役所に帰ってから課長と相談したようで、2日ほどたってOKの返事。ぷかぷかが日々やっていることをみての判断だったと思います。多分おもしろいものを作ってくれるんじゃないか、と。下の写真のような。 さてどういうデザインにしようかと考えながらぶらぶら歩いているときに、ヨッシーの描いた歯医者に行って虫歯だらけの口をガバッと開けている絵を見つけました。あっ、これをブースの入り口にしたら絶対おもしろい、と思いました。で、その絵をアート屋わんどの職員コンドーに見せ、段ボールで入り口をデザインしてもらいました。 ブースの入り口の装飾だけでなく、テントの屋根に段ボールで作った直径1メートルくらいのカボチャ(地産地消のシンボル)をのせたいと言い出したので、Kさんは 「え〜〜!」 とびっくり。心配になって総務課に相談したら、 「そんなあぶないことはいかん!」 といわれたそうで、すぐ私に「だめみたいです」と電話がありました。 「絶対に落っこちないようにするから」 と、絵を描いて説得しました。 実際屋根にのせてからは落ちなかったのですが、のせる途中で落っこちてきてちょっと大変でした。下の写真の直後、真っ逆さまになって落っこちたのです。 区民まつりで配るチラシもデザインすることになり、地産地消をやっているお店の情報を入れてくれるように頼まれました。Kさんから送られてきたお店のデータはお店の名前、営業時間、電話番号などのテキストデータで、新人のKさんとしては一生懸命作ったデータでした。それを 「あの〜、こんなの見ても、誰もお店に行こうって思わないんじゃないですか。」 って、私が正直に言ったので、えらくめげたみたいでした。 「テキストじゃなくて、楽しい絵地図で行きましょう。ぷかぷかさんが描くと、絶対楽しい絵地図になります。お店のシェフの似顔絵も入れると、あっ、こんな人がつくるんだ、ってわくわくしてお客さんはいっぱい来ますよ」 と丁寧に説明し、Kさんは納得したようでした。 ここから絵地図の物語がはじまります。 似顔絵も入れるとなると、チラシには入りきらないので、もっと大きなスペースが欲しいと言い、KさんはA1サイズの大きなパネルを用意してくれたのですが、似顔絵は原寸大で入れたい、とまたわがままを言い、結局テントの横の壁いっぱいに貼り出すことにしました。 シェフの似顔絵を描きに行きました。 そうやってできあがった絵地図がこれ 予想をはるかに超えた楽しい絵地図ができあがりました。 区民まつりの朝、通りかかった区政推進課の課長に 「これ、一日で捨てちゃうの、もったいないですよ。一週間くらい区役所のロビーに貼り出しませんか?」 という提案をしました。 しばらくして課長から連絡があり、絵がヨレヨレになっているので、きれいにパネル張りにして展示したい、見積もりを取って欲しい、ということでした。 知り合いの額縁屋さんに連絡。見積もりを取ったところ10万円。そんなお金出してくれるのかなぁ、と思いながら課長に電話。これがあっさりOK. ヨレヨレになった絵地図をパネル張りにしました。 できあがったパネルを区役所に持って行ったら、Kさんと係長は「ひゃ〜すごい!」とびっくり。せっかくなのでロビーに飾る前に除幕式をやりましょう、ということになりました。 区長が出席しての除幕式でしたが、途中でぷかぷかさんが踊り出し、はずみでパネルにかぶせてあった白い幕が落っこちてしまうというハプニングがありましたが、ま、ぷかぷからしくていい、とみんな大笑い。 この一連の仕事でできた信頼関係の中で、区役所で行われる人権研修会の講師を依頼されました。私一人で行ってもなんかつまらない感じがしたので、人権問題の当事者であるぷかぷかさんを三人ほど連れて行って講師をやってもらいました。ぷかぷかさんが行けば、今までにないおもしろい人権研修会になるという確信がありました。まとまった話はむつかしいので、いろいろ質問してもらいました。「給料は何に使いますか?」「仕事で何が一番楽しいですか?」「休みの日は何をしていますか?」といった質問に答えました。それでもみんな新鮮な印象を持ったようで、たくさんの人がアンケートを書きました。人権研修会はいつも硬い話でアンケートはほとんど書かないそうです。こんなにたくさんアンケートが集まったのは初めてです、と担当の方はびっくりしていました。 これが4万円からはじまった物語です。そもそも地産地消の打ち合わせに私は出たことがなかったのですが、たまたまあの日時間が空いていて、打ち合わせにでて、思いつきで4万円でブースのデザインやらせてくれませんか、と提案したのです。そこからこんなにもいろいろな物語がはじまったのです。 これがきっかけで区役所とのおつきあいの幅がグンと広がりました。区民まつりの地産地消ブースのデザインは毎年のように依頼されます。 新人のKさんにとっては本当に大変な1年だったと思います。でも大変だったからこそ、人生の幅がグンと広がったのではないでしょうか。その広がりを新しい職場でも生かしてもらえたら、と思っています。本当にお疲れさまでした!
「決して忘れない」という言葉はどこへ行ってしまったんだろう

神奈川新聞「時代の正体」に、相模原障害者殺傷事件の犯人に面会に行った話が載っていました。 www.kanaloco.jp 《 事件からまもなく2年。社会は変わったか。そんな問いは無意味の思えるほど風化が進み、事件直後にあちこちで耳にした「決して忘れない」という言葉がむなしく感じられる。 》と、記事にありました。そういえばあれだけみんな口にしていた「決して忘れない」という言葉はどこへ行ってしまったんだろうと思います。 「決して忘れない」をいうだけでは、差別や偏見を許容する社会は、何も変わりません。 障がいのある人たちのグループホーム反対を叫ぶ人たちがいます。「障がい者はこの地域に来るな」「ここに住むな」といってるのです。「障がい者はいない方がいい」といった犯人と全く同じ発想です。障がいのある人たちを社会から排除する、という動きは、こんなふうにあちこちにあって、あれだけの事件がありながら、社会は何も変わっていないことになります。 事件を忘れない、というところにとどまるのではなく、日々の暮らしの中で立ち現れる差別や偏見とどう向き合うのか、それに対して何をするのか、ということこそ大事な気がします。 こんな関係を作り続けること、これこそがぷかぷかが日々やっていることです。
100年先を見据える
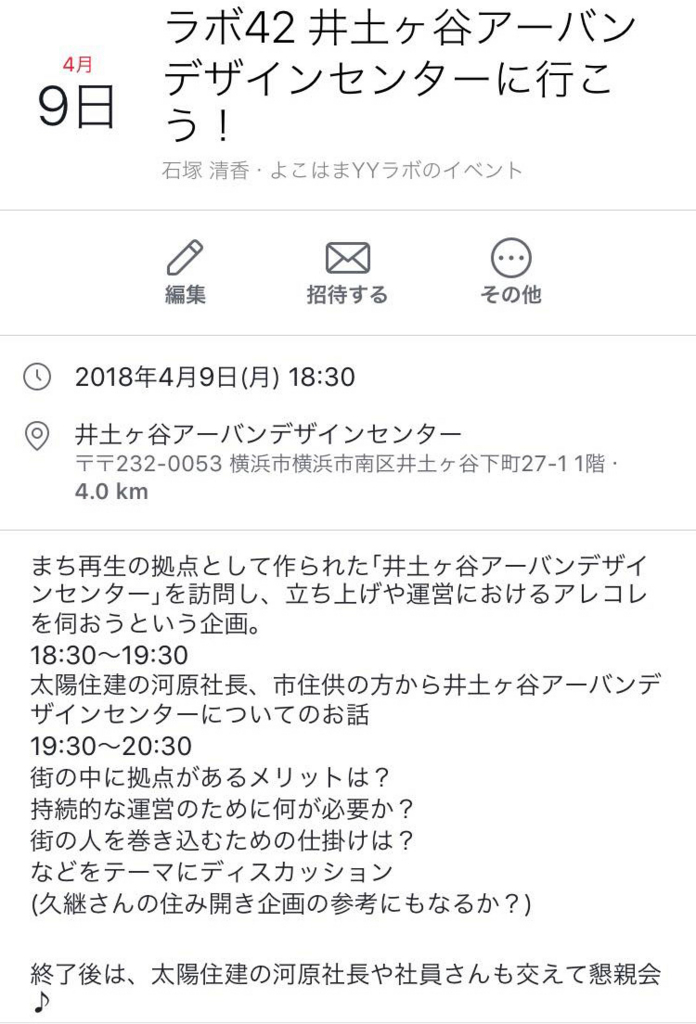
昨夜、井土ヶ谷アーバンデザインセンターで開かれた「よこはまYYラボ」のイベントに行ってきました。ぷかぷかも15分ほどプレゼンやらせていただきました。「街の人を巻き込むための仕掛けは?」ということも話題に上がっていたので、ぷかぷかがやってきたことをいろいろお話ししてきました。 太陽住建社長の河原さんは、会社の説明のあと、ゆるいつながりが思ってもみない価値を生んだ、というようなお話をされました。 クジラの大きな絵は、街の人たちを巻き込んで描いた絵。絵を一緒に描くことで、障がいのある人たちとのいい関係をたくさん作りました。 ぷかぷかのアートを紹介 ぷかぷかのおいしいお惣菜を紹介 おひさまの台所のごちそうが並びました。 太陽住建会長の河原さんが100年企業を目指す意味を語られていました。今いろんな節目節目で経営の判断をしているのですが、100年先の人の評価に耐えられるような判断をしたい、とお話しされ、いやぁすごいなぁ、と思いました。 100年の歴史を見据えながら会社を経営していくってすごいですね。目の前にぶら下がる人参で判断するのではなく、100年先を見据えての判断をしたい、というお話でした。 www.taiyojyuken.jp ぷかぷかにとって100年先を見据えるってどういうことなのかと思いました。福祉事業所であっても、そういう歴史視点は必要だと思います。100年先の人が振り返ったとき、納得できるような価値をぷかぷかは創り出しているのかどうか、です。 ぷかぷかはタカサキが障がいのある人たちの惚れ込んだところから出発しました。惚れ込む、というのは個人的なものです。でも彼らのそばにいて感じる「ほっこりするようなあたたかさ」は一人で味わうにはもったいないと、「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」「その方がトクだよ」というメッセージをたくさんの人に向けて発信し続けてきました。メッセージだけではなく、リアルにそのことを感じられる、障がいのある人たちとのいい関係、いい出会いを作ってきました。 お店、パン教室、演劇ワークショップ、アートワークショップ、ぷかぷかマルシェ、運動会などで、「いっしょにいるといいよね」って思えるようなすばらしい出会い、関係をたくさん作ってきました。 「いっしょにいると心ぷかぷか」というプロモーションビデオも作りました。これは障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージを映像化したものです。 そういう中で、少しずつぷかぷかのメッセージに共感する人が増え、たくさんのファンができました。社会の中で排除されることの多い障がいのある人たちですが、彼らを排除しないどころか、彼らのファンだと言う人たちを作ったことの意味は大きいと思います。 彼らのファンになることは、人間としての幅が広がることであり、豊かになるということです。そしてそんなファンが増えるということは、社会が少しずつ豊かになる、ということです。そういう歴史を少しずつ作っている、といっていいと思います。 あのおぞましい相模原障害者殺傷事件は「障害者はいない方がいい」という強烈なメッセージであり、障がいのある人たちを排除する社会を象徴する事件でした。でも、それにひるむことなく、ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」と言い続け、その「リアル」を作り続けてきました。 それは理屈っぽい話ではなく、彼らに惚れてしまった私自身の生き方の問題だったと思います。どこまでも彼らといっしょに生きていきたい、という生き方。 100年先を見据えての判断というのはなかなかむつかしいですが、日々、自分の生き方としてやっていくことはできます。100年先の人が見ても恥ずかしくない生き方です。
私は?よくわかりません状態でした。

セノーさん、今日はお父さんと一緒に映画を見に行ったようで、お父さんのFacebookに、本人はおもしろかったそうですが、私はよくわかりません状態でした、と書いてあって、笑ってしまいました。 www.facebook.com この謙虚さがいい!と思いました。本当にいいお父さんです。 セノーさんに限らず、どのぷかぷかさんもわからないこと、感心することがたくさんあります。そのわからなさに私達がどこまで謙虚に向き合えるか、というところで、そこから豊かなものが生まれるかどうかが決まるのだと思います。 セノーさんが選んだ映画のホームページです。 servamp-movie.jp 私はこの映画のストーリーを読んでも、ついていけないというか、どういう映画なのかよくわかりませんでした。でもセノーさんは「あっ、これはおもしろい!」と思って、お父さんを誘ったのだと思います。セノーさんて、ああ見えて、実はすごい人なんだとあらためて思いました。そういうことを感じさせないところがいいですね。人間ができているというか…。タカサキとえらい違いです。 養護学校でセノーさんを担任をしている頃、私の誕生日に、その日(1949年4月30日)に発行された新聞のコピーをプレゼントしてくれたことがあります。活字がずいぶん古めかしい新聞でした。あとで聞いた話によると新宿のヨドバシカメラでそういうサービスをやっていたそうで、そこまで取りに行ったみたいでした。どこでそういうサービスを調べたのかわかりませんが、本当にびっくりしました。誕生日に発行された新聞をプレゼントするという発想がすばらしいし、それを実行する力がすばらしいと思いました。 そんなセノーさん達とおつきあいしていると、どう考えても彼らは障害者であり、私たち健常者の支援が必要な人たち、とは思えないのです。思えない、という謙虚なところでおつきあいしていると、毎日いろんな新しい発見があって、いい勉強させてもらっています。そして何よりもそんな彼らとのおつきあいが楽しいのです。
注文の多い料理店・序ー手話による表現

1月の表現の市場では、『注文の多い料理店・ぷかぷか版』の「序」の部分をデフパペットシアターひとみのみなさんにやっていただきました。pvプロボノの信田さん、高橋さん、藤木さんに記録を撮ってもらい、その編集が終わりました。最初カメラ6台も使って撮る意味がよくわからなかったのですが、この映像を見て納得できました。6台で撮った映像を編集することで、こんなすばらしい映画ができあがるんですね。なんとなくぼんやり見ていたあのシーンが、一つの作品=映画になっていることにおどろきました。映像クリエイターの人たちのチカラですね。pvプロボノの人たちに感謝!です。 「注文の多い料理店・序」はとても美しい日本語です。それを手話で表現するのは、本当に大変だったと思います。デフパペットシアターひとみの人たちの底力を見た気がしました。 味のある文字はぷかぷかさんです。存在感のある文字です。 www.youtube.com 演劇ワークショップ、表現の市場の映像は現在編集中です。8月4日(土)みどりアートパークホールで上映する予定です。近くなりましたらお知らせします。
8年前 一本の柱を立てた。

4月14日(土)のぷかぷか8周年のイベントで、演劇ワークショップで歌った「あの広場のうた」を歌う予定で、今、毎日みんなで練習しています。歌いながら、あらためて、ぷかぷかって、みんなにとってとても大切な広場だったんだなという感じがしています。 ぷかぷかにはいつもの朝、いつもの夜がやってくる。 あれ、ここはどこだっけ、とふと思うことがあっても、ここはいつもの場所。 でも、どこかちがう。ここはどこかに似ている。 大人も子どもも、犬や鳥たちも、虫たちも集まる、あの広場みたい。 耳をすませば見えてくる。(ここの言葉の使い方がすばらしい。この歌を作った萩京子さんのセンスです。) 目をみはれば聞こえてくる。 耳をすます、目をみはる。 そうすると、少しずつ、少しずつ、 見えてくるものがある、聞こえてくるものがある。 歌が生まれ 人は踊り出し 物語がはじまる あの広場がここに 広場から たくさんの物語が生まれた。 みんなの広場だったから ステキな物語が 次々に生まれた。 障害者は性犯罪を起こすかも知れない、などとグループホームに反対する大人がいる社会は悲しい。 その一方で、ぷかぷかに来る子ども達はこんな物語を作った。 この子ども達が大きくなって、社会を担う頃、どんな社会を作るのだろうと思う。 三枚の写真から見える物語には希望がある。 前に向かって、私たちの背中を押してくれる。 1000を超えるぷかぷか日記にはたくさんの物語が詰まっている。 障がいのある人たちは、あれができないこれができない人たちじゃない。 社会の負担でもなく、社会のお荷物でもない。 社会を耕し、社会を豊かにする存在なんだ、という物語は、 たくさんの人に希望をもたらした。 (そんな物語たちを本にまとめようと思っています。楽しみにしていて下さい) 障がいのある人たちに惚れ込み、 彼らと一緒に生きていこうと 8年前 一本の柱を立てた。 柱のまわりに 少しずつ 少しずつ 人が集まり 歌が生まれ 人は踊り出し 物語がはじまった。 昔 広場に一本の柱 ここに立てよう 目には見えない柱を 昔 広場に一本の柱 ここではじまったぷかぷか いまここで www.youtube.com ♪ いまはいつだろう いつもの朝 ここはどこだろう いつも場所 いまはいつだろう いつもの夜 ここはどこだろう いつもの場所 でもどこかちがう ここはどこかに似ている おとなもこどもも 犬も鳥たちも 虫たちも集まる あの広場みたい 耳をすませば見えてくる 目をみはれば聞こえてくる 少しずつ 少しずつ 歌が生まれ 人は踊り出し 物語がはじまる あの広場がここに 昔 広場に一本の柱 ここに立てよう 目には見えない柱を 昔 広場に一本の柱 ここではじまったぷかぷか いまここで ♪
筑豊の「虫の家」で上映会とお話

7月21日(土)13:30〜16:00 福岡県の筑豊にある筑豊共学舎「虫の家」(福岡県鞍手郡小竹町大字御徳167番地の30)で「相模原障害者殺傷事件2周年・追悼の集い」があります。そこでぷかぷかのプロモーションビデオカナダ版の上映と相模原障害者殺傷事件についてトークセッションします。問合せは09496−2−6003 gujinan@utopia.ocn.ne.jp 「虫の家」のホームページです。私たちの「障害」観は、短い文章ですが、本質的なところをズバッと書いています。 mushinoie.webnode.jp ここの代表の高石さんが去年の11月、北九州市で行った上映会とトークセッションに参加したことがきっかけで、今回の企画が立ち上がりました。その高石さんの思いは みんな“ぷかぷか”になれたら素晴らしい 髙石 伸人 高崎明さんが最初に「虫の家」に来られたのは1999年の夏でした。その際にエアコンを設置したので覚えています。当時、養護学校のセンセイであった高崎さんは、既に「全国ボランティア研究集会」などでワークショップのファシリテーターとして活躍し、全国区の名の知れた人でした。「虫の家」に来られたその時も、水俣で胎児性の若い患者の皆さんとワークショップをやった後、横浜に帰る途中で立ち寄ってくれたのだったと記憶しています。 「虫の家」は1986年にポリオや脳性マヒの青年たちを中心に「街に出よう、街を変えよう!」をテーマに、「自立生活センター」をモデルにして始めた、いわば地域活動拠点(たまり場)でした。ボクは当初からソーシャルワーカーとして、会の事務局的な役割を担ってきたことから、たまたま条件が上手く転んで、自宅敷地を拠点建設の用地として提供する羽目になりました。それから32年、今では半数以上が代替わりして、8人の知的障害のメンバーを中心に、法律上の「地域活動支援センターⅢ型」の運営を柱に、ハンセン病資料室の開設や人権問題の学習会を開くなど、筑豊ではちょっと知られたNPO団体です。 そんなボクたちにとっても、一昨年に起きた「相模原障害者殺傷事件」は衝撃的でした。これまで自分たちが問いかけてきたことが何だったのか、改めて、考えさせられる出来事でした。深い霧の中にいるような気分が続いているある朝、某テレビ局のニュース番組に横浜の「ぷかぷか」の日々が映し出されていて、あの飄々とした、自身が「ぷかぷか」そのものの高崎さんの、当時よりちょっと老けた懐かしい顔が何度も画面に登場したのでした。その前後に、朝日新聞の全国版でも紹介され、昨年は北九州での「映画と講演のつどい」で話を聴く機会をいただきました。「障害者を街の宝に」という願いの詰まった「ぷかぷか」の実践にこそ、相模原事件に対抗する、あるいは根っ子にあるものを溶解させるヒントがてんこ盛りなのだと気づかされたことです。生の高崎さんから届けられる「ぷかぷか」なメッセージを近隣の皆さんとも分かち合って、事件の本質にどのように向き合うかを考えていきたいと思います。是非、ご参加ください。 (NPO法人ちくほう共学舎「虫の家」事務局長) というわけで、「虫の家」でぷかぷかの映画とお話をします。できれば高石さんと相模原事件をテーマにトークセッションができたらと思っています。あまり硬い話にならず、ゆるっとゆるむような話になれば、と思っています。 先日ぷかぷかの近くで障がいのある人たちのグループホームの反対運動がありました。「障害者はここに住むな」「障害者はここにはいない方がいい」といってるわけで、これは「障害者はいない方がいい」と言っていた相模原障害者殺傷事件の犯人の考えと全く同じです。障害者がここに住むと犯罪、特に性犯罪が心配、といった声もありました。説明会に私も参加しましたが、もう話し合いでどうこうなる雰囲気ではありませんでした。 「障がいのある人たちのことを知らない」「おつきあいがない」というだけなのですが、たったそれだけのことがここまで人と人を分断してしまうのです。相手の話を聞きながら正直悲しくなりました。 で、思いついたのが、その地元の子ども達を相手にぷかぷかさん達と一緒にパン教室をやることでした。パン教室は単純に楽しいです。子ども達は大喜びでした。そこに当たり前のようにぷかぷかさん達がいました。 pukapuka-pan.hatenablog.com 相模原事件を超える社会は、優生思想云々のむつかしい話をするのではなく、こうやってお互いが楽しいねって思えるような関係をコツコツ作っていくことだと思います。 ぷかぷかはできて8年目になります。その間、たくさんのファンを作ってきました。「ぷかぷかさんが好き!」というファンは、「障害者はいない方がいい」という相模原障害者殺傷事件の犯人と正反対の位置にいます。正反対の位置するような人をどうやって作り出したか。 ファンを作るコツは障がいのある人たちを社会にあわせたりせず、そのままでいてもらうことです。ぷかぷかはできた当初、接客の仕方がわからず、講師を呼んで接客の講習会をやったことがあります。何のことはない「接客マニュアル」通りやりなさい、ということだったのですが、マニュアル通り振る舞うぷかぷかさんの姿が気色悪くて、もう一日でやめました。で、どうしたかというと、もうマニュアルなんか使わず、ぷかぷかさんそのままで行こう、ということにしたのです。 決して接客がうまいわけではないのですが、ぷかぷかに来るとなんかホッとする、と言うお客さんがたくさん現れました。接客マニュアル通りやるとか、社会にあわせるとかしなくて、彼らのそのままの姿にファンがついたのです。 「障害者はいない方がいい」といわれた彼ら自身が、彼らのそのままの姿でファンを作り、相模原障害者殺傷事件を超える社会をコツコツ作っているのです。ともすれば「優生思想」云々と硬い話に終始する私たちよりも、はるかに確実に社会を変えているのです。そのことに私たちは気がついた方がいいと思います。 事件後「障害者を守る」という動きが活発になりました。「守る」というのは「囲い込む」ことであり、「生かさず、殺さず」になってしまいます。 「ぷかぷか8周年」にも書いているように、ぷかぷかは外部とのコラボを通して、ぷかぷかさん達と一緒にどんどん前に進みます。守るどころか、垣根をどんどん取っ払って、新しい価値を創り出そうとしています。彼らがいてこそ、社会は豊かになる。そういったことをたくさんの人たちと共有したいのです。 こういったことをやり続けることが相模原障害者殺傷事件を超える社会をダイナミックに作っていくのだと思います。 ダイナミックに作っていく、いい言葉ですね。それくらい元気にやりましょう! pukapuka-pan.hatenablog.com
ぷかぷか8周年
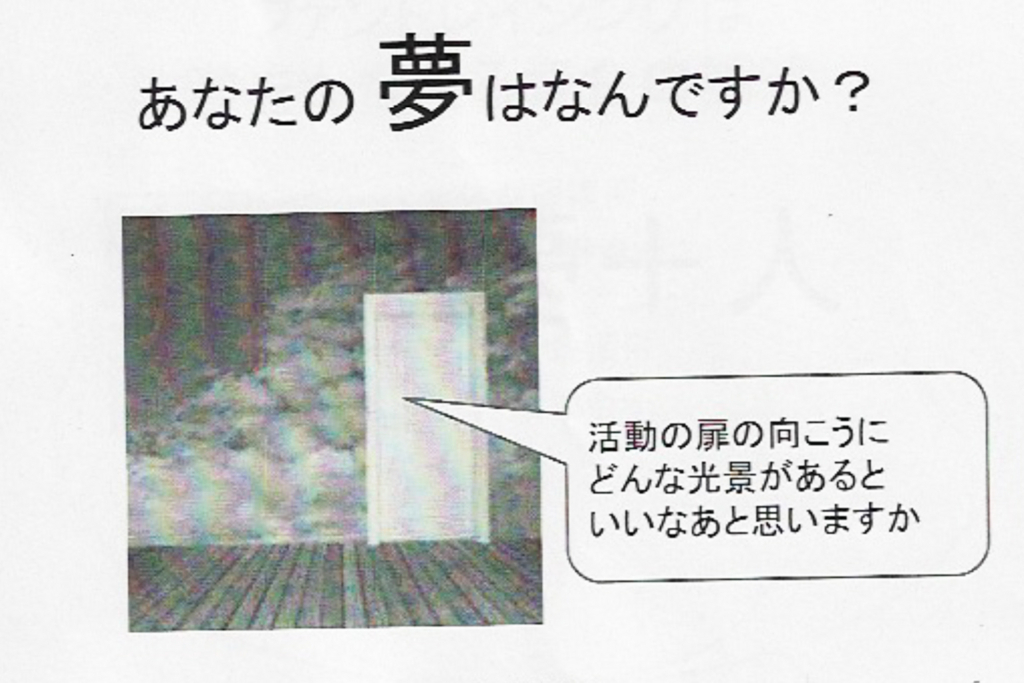
この4月でぷかぷかは8年目を迎えます。開設当初のことを思えば、潰れもせず、よくぞ持った、とほめてやりたいくらいです。それくらい初期の頃は大変でした。8年目にしてようやく組織全体が前に向かって動き始めたと実感しています。 先日横浜市市民活動支援課主催の「ファンドレイジング講座」に行ってきました。NPOが活動のための資金を集めるにはどうしたらいいか、をテーマにした講座です。ぷかぷかはいろいろやっていますが、お金を集めることは全くの下手くそで、いつも貧乏です。パンやお惣菜などの商品はそこそこ売れるのですが、演劇ワークショップなど非収益事業も含めた活動全体を合わせると、恥ずかしいくらい貧乏です。で、まぁ、すがるような思いで講座に参加したわけです。 冒頭、こんな言葉がありました。 今更ながらNPOの活動の意味を思いました。 「こんなことを実現したい」という「夢」。その「夢」の実現に向かっていろいろ活動を展開するのがNPOだと。そうか、そうだよな、NPOって、「夢」を追いかけるんだよな、ってあらためて思ったのでした。 ぷかぷかは「障がいのある人もない人もお互いが気持ちよく生きていける社会」を目指しています。社会を目指す、なんていうと壮大な夢という感じですが、それを単なる夢で終わらせないためにどうしたか。 ぷかぷかは「彼らといっしょに生きるといいね」と思える関係を日々具体的に作ってきました。毎日発信しているFacebookを見てもらえばすぐにわかります。「夢」を単なる「夢」で終わらせず、日々小さなことの積み重ねを続けることで、「夢」の実現に向けて一歩一歩確実に前に進んできたのです。 演劇ワークショップにこれだけエネルギーが注げるのも、「夢」の実現に向けて確かな一歩を踏み出せると確信しているからです。ヨコハマアートサイトが昨年ぷかぷかの企画に対して満額回答をしてくれたのも、「夢」の実現の確かさに共感したからだと思います。「夢」を単なる「夢」で終わらせない、確かなビジョン。それを企画書から読み取ってくれたのだと思います。 日々のお店の運営も、パン教室も、アートのワークショップも、ぷかぷかさんとのいい関係を作り続けています。そんな中で見えてきたことは、彼らといい関係を作ることで、私たち自身が人として豊かになれる、ということです。だから彼らは社会に必要、ということ。いろいろできないから何かやってあげる対象ではなく、そのままの彼らが社会に必要、ということ。そのことをたくさんの人たちと共有できたことはとても大きいと思います。 共生社会を目指そう、とか、共に生きる社会を目指そう、といった抽象的な話ではなく、リアルに彼らといっしょがいいよね、って思える関係をぷかぷかは日々の活動の中で作ってきたのです。 そのリアルさの中で、たくさんのファンができました。そのファンの中から「ぷかぷかプレミアム会員」の提案までありました。年会費1万円です。商品の割引、といったちゃちな特権ではなく、たとえばぷかぷかさんと一緒に一泊旅行に行ける特権です。ぷかぷかさんともっと濃厚なおつきあいのできる特権です。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージをはるかに超えたものをこの提案には感じます。 8年目を迎えてぷかぷかが大きく動き始めたことがあります。それは外部の人たちとのコラボ=協働です。コラボすることで、新しい価値を生み出そうということです。 先日紹介したビオアグリとのコラボは具体的に動き始めました。 pukapuka-pan.hatenablog.com ビオアグリの代表とは初めてお会いしたのですが、ちょっと話をしただけで通じるものがあり、畑で話をしながら、その場で新しい価値を生み出すようなコラボをしましょう、ということになりました。それがもう実現しつつあります。 ビオアグリの畑で取れた黒豆を使ったパンを焼きました。 淡路島ではハード系のパンがないので、ぷかぷかのハード系のパンを近々販売することになっているのですが、向こうの畑で取れたおいしい黒豆を使ったパンはまさにコラボの商品です。その商品にはぷかぷかがデザインしたラベルを使います。ビオアグリのメンバーさんの似顔絵をぷかぷかさんが描き、それを使ったラベルを今製作中です。文字もぷかぷかさんが描きます。近々東京に出店をだすそうで、そこでもコラボ商品、ぷかぷかの商品を並べてくれます。 作り手がどんな人か、似顔絵は写真よりもはるかにその人のあたたかさを伝えます。コラボの商品価値をグ〜ンと引き上げます。ぷかぷかさん大活躍です。これにぷかぷかさんの描いた商品の文字が重なります。 イメージとしてはこんな感じのラベルができます。 昨年旅行で行った上野さんのいろいろ米を使ったパンができました。上野さんのライ麦は以前から使っていますが、いろいろ米を使ったパンは初めてです。いろいろ米はご飯として食べるだけでなく、パンとして食べてもおいしいことがよくわかります。ぜひお試し下さい。いろいろ米とパンのコラボで新しい味が生まれたのです。 上野さんは4月14日(土)の8周年イベントにやってきます。上野さんははっぱを使った虫作りの名人です。この虫を作るワークショップをやります。栃木のイチゴも持ってきます。これはもう絶対に来なきゃソン!です。 www.youtube.com 今年の夏の旅行も上野さんのところへ行きます。 川野さんという人が天草でおいしい甘夏を作っています。 pukapuka-pan.hatenablog.com このブログに登場している川野さんの家に着くなりうんこした息子が今淡路島のビオアグリのメンバーになり、ここからビオアグリとのコラボが始まりました。 川野さんの甘夏を使った新しい甘夏パンができました。今年はフランス生地の中に甘夏ピールを練り込んでいます。以前の甘夏パンよりもグ〜ンとおいしくなっています。 5月にはプロダクトマネジャー、副施設長が川野さんのところまでいって、甘夏の山を見学し、一晩泊まって川野さんお話を聞いてきます。 甘夏パンにまた新しい物語が加わります。楽しみにしていて下さい。 昆布を食べて環境を守ろうという里海イニシアティブさんとのコラボも検討中です。 satoumi-i.com 横浜市地域貢献企業として認定されている協進印刷さんとのコラボも検討中です。 www.kyoshin-print.co.jp それぞれのコラボで、どんな新しい価値が生み出せるのか、楽しみなところです。 ぷかぷかは8年目を迎え、更に進化していきます。どうぞお楽しみに。 4月14日(土)は8周年を記念したパチパチマルシェをやります。詳しくは近日中にお知らせします。ビオアグリの製品販売もします。 こんなかわいいアラレちゃんも登場します。
ヨコハマアートサイト 今年も満額回答を目指して

ヨコハマアートサイトの「横浜で地域と共に活動する芸術文化事業」に今年も応募しました。ぷかぷかさんと地域の人たちが一緒になって行う演劇ワークショップの企画です。 ヨコハマアートサイト 昨年は満額回答の100万円ゲットしたので、今年もそれを目指してかなり気合いを入れて書きました。やる内容は同じ演劇ワークショップなのですが、それを去年とはなるべくちがう言葉で表現します。限られた枠の中で、どこまで思いを書ききれるか、が勝負です。 その主なところを報告します。 《 事業のねらい 》 障がいのある人たちと一緒に生きていくと、社会が豊かになると考える。そのことを目に見える形で表現するために障がいのある人たちと一緒に演劇ワークショップをおこなう。 《 対象となる地域の状況や課題、魅力をどう捉えているか 》 ぷかぷかが霧ヶ丘に誕生して8年。開設当初は障がいのある人たちへの偏見がひどく、人権侵害といっていいほどのバッシングがあった。そういった雰囲気の中で尚も「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」というメッセージをホームページやFacebookで発信し続けてきた。障がいのある人たちを理解してもらうというのではなく、どこまでも彼らの魅力を伝えるメッセージ。Facebookには、多い日は10本くらいの記事をアップした。日々のお店での活動、アートワークショップ、パン教室、演劇ワークショップなどを通して「彼らとはいっしょに生きていった方がいいね」と素直に思えるような関係をたくさん作ってきた。その結果、彼らを理解するとか、福祉事業所を応援するとかではなく、純粋に彼らのファンができた。最近は年会費1万円のぷかぷかプレミアム会員を作ってはどうかと提案する熱烈なファンも現れた。商品の割引ではなく、彼らといっしょに一泊旅行に行ったり、いっしょにカラオケに行ったりする特権が欲しいという。1万円払ってでも彼らと濃厚なおつきあいをしたいという人たちだ。彼らが生み出す新しい価値に気がついた人たち。地域社会が確実に変わってきている。 《 実施活動における文化芸術が果たす役割 》 ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを日々発信しているが、演劇ワークショップはそのメッセージを、芝居という目に見える形にしてくれる。理屈っぽい言葉ではなく、誰にでも感じとってもらえるメッセージだ。そのために、今まで障がいのある人に何の関心もなかった人たちにも幅広くメッセージを届けることができたと思う。また演劇ワークショップに参加すると、障がいのある人たちに向かって素直に「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」と思えるようになる。「共生社会」とか、「共に生きる社会」といった抽象的な話ではなく、リアルにそう思える関係ができる。芝居を作る、という文化芸術活動が、障がいのある人たちとの新しい関係を作ったと言える。しかもその関係は新しいものを創り出すクリエイティブな関係であり、それこそ障がいのある人の持つ新しい可能性、新しい価値を掘り起こしたとも言える。 《 「継続活動助成」の場合、昨年度と比べて工夫した点 》 小道具、大道具などの制作が大変なことと、事業の継続を考えて、演劇ワークショップに直接かかわるアート部門のスタッフを増やすことにした。演劇ワークショップの継続は、単なるテクニカルな問題だけでなく、障がいのある人たちの置かれた社会的状況の中で、演劇ワークショップ手法をどういう形で生かすか、ということだ。そのためには、その社会的状況をよく理解し、芝居作りが好きで、何よりも障がいのある人たちと一緒に生きていきたいという思いがあるかどうかがとても大事になってくる。そういう人を育てることを今期の大きな目標としたい。 《 今年度の達成目標 》 宮澤賢治作『ほらクマ学校を卒業した三人・ぷかぷか版』をみんなで作り、みどりアートパークのホールの舞台で上演する。障がいのある人たちとの芝居作りを、新しい文化の創出、といった観点から再評価していく。相模原障害者殺傷事件のことをいつも忘れず、事件へのメッセージとして演劇ワークショップを評価していく。 《 団体の目的・特色 》 障がいのある人たちに惚れ込み、彼らと一緒に生きていきたくて、養護学校定年退職後「ぷかぷか」を立ち上げた。「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを日々Facebookなどで発信し、「いっしょがいいね」と思える関係をお店、パン教室、アートワークショップ、演劇ワークショップ、運動会などのイベントで作ってきた。たくさんの方がぷかぷかさんと出会い、地域の中でたくさんのファンができた。ファンの存在は、ぷかぷかさんが地域を耕し、豊かにしていることを物語っている。あれができないこれができないと社会のマイナス要因でしかなかった「障害者」がぷかぷかにあっては、地域を耕し、地域を豊かにする存在になっている。障がいのある人たちの社会における新しい価値を掘り起こしたといっていい。 《 団体の沿革・経歴 》 2009年9月NPO法人ぷかぷか設立 2010年4月就労継続支援B型事業所として「カフェベーカリーぷかぷか」「ぷかぷかカフェ」オープン 2014年6月お惣菜屋「おひさまの台所」オープン 2015年2月アートスタジオ「アート屋わんど」オープン 第一期演劇ワークショップ 2014年6月〜11月 第二期演劇ワークショップ 2015年9月~2016年2月 第三期演劇ワークショップ 2016年8月〜2017年1月 第四期演劇ワークショップ 2017年8月〜2018年1月 2015年12月 演劇ワークショップが高く評価され読売福祉文化賞受賞 2016年 5月プロモーションビデオ「いっしょにいると心ぷかぷか」完成 2017年 6月プロモーションビデオ「いっしょにいると心ぷかぷか−2」完成 相模原障害者殺傷事件へのメッセージが評価され、2017年7月NHKで紹介される 《 これまでの活動実績 》 [平成27年度] 第二期演劇ワークショップの開催 2015年9月〜2016年2月 2月にみどりアートパークホールでみんなで作った芝居『みんなの生きる』を発表。社会の不満、イライラから自由なぷかぷかさんを表現した。 区民まつりで地産地消ブースをデザインし、発表。10月。50張りあるブースの中でいちばん楽しいブースのデザインとして評価された。地産地消サポート店の大きな絵地図(縦2m、横3.6m)を制作し、発表。絵地図は高く評価され、緑区役所のロビーに展示された。 アートのワークショップで、地域の人たちといっしょに大きなクジラの絵を制作、発表 [平成28年度] 第3期演劇ワークショップ 2016年8月〜2017年1月 1月にみんなで作った芝居『セロ弾きのゴーシュ・ぷかぷか版』をみどりアートパークホールで発表。 緑区民まつりで地産地消ブースをデザインし、発表。「野菜たちのお祭り」というテーマでデザインしたブースはとても好評だった。10月 アートのワークショップで段ボール製のファッションモデルを地域の人たちといっしょに制作。ぷかぷか秋のマルシェでファッションショーを行い、そのパレードにはNHKが取材に来た。演劇ワークショップの舞台にも登場させ、ネズミのシーンで「夜風とどろき」の歌を歌いながらダンスを踊った。 [平成29年度] 第4期演劇ワークショップ 2017年8月〜2018年1月。1月にみんなで作った芝居『注文の多い料理店・ぷかぷか版』をみどりアートパークホールで発表。ぷかぷかはみんなの大切な広場になっていると『あの広場のうた』をみんなで歌い、とても好評だった。 10月の緑区民まつりでは今年もまた緑区役所から依頼で地産地消のブースをデザイン。3年続けてデザインの依頼を受けた。「野菜たちの結婚式」というテーマでデザインし、好評だった。 ぷかぷかのアートを企業に売り込む営業資料をサービスグラントと協働で制作。企業の力を借りて、ぷかぷかのアートで社会を豊かにする活動がスタートした。 進行役講師料、ピアニスト謝礼、舞台製作費、会場費、記録映画作成費など総予算は2,175,000円。そのうち100万円を申請しました。 ヨコハマアートサイトは予算の半額しか申請できません。去年は予算が2,035,000円だったので、本当に満額回答でした。今年も満額回答を目指した書いたのですが、思いが審査員に届けば、と思っています。 演劇ワークショップ開催日は2018年8月18日(土)、9月22日(土)、10月20日(土)、11月17日(土)、12月15日(土)、2019年1月19日(土)、1月26日(土) 時間は毎回9時~午後4時半です。 1月27日(日)は『表現の市場』の舞台でできあがった芝居を発表します。参加を希望される方は連絡下さい。045−453−8511 ぷかぷか事務所 高崎 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp なるべくなら全部参加して欲しいのですが、無理な方はご相談下さい。
北秋田に ぷかぷかがやって来る!

北秋田から電話があり、5月26日(土)のイベントのチラシを作って欲しい、というものでした。 pukapuka-pan.hatenablog.com チラシのタイトルはなんですか?と聞くと 「北秋田に ぷかぷかがやって来る!」 だそうです。うれしいですね、そんなふうにぷかぷかを受け止めてもらえるなんて。 ワークショップ、上映会、トークセションを通して、「ぷかぷか」の風を北秋田に吹き込みたいようです。ぷかぷかの理念、なんてまじめなところだけでなく、ぷかぷか的発想、ぷかぷか的にぎわい、ぷかぷか的だらだら時間、ぷかぷか的まとまりのなさ、ぷかぷか的適当さ、ぷかぷか的思いつき、ぷかぷか的おもしろさ、みたいなものが、わ〜っと熱くうずまくような、エネルギッシュな風。 会場は繁華街に近いところだそうで、だったらワークショップではみんなで段ボールを使って怪獣を作り、怪獣の叫び声を上げながら、北秋田の繁華街を練り歩こうって提案しました。障がいのある人もない人もごちゃ混ぜで、叫び声を上げると、すっきりいい気分です。その時の開放感こそがぷかぷかが目指すもの。 場所は北秋田ふれあいプラザ コムコム 多目的ホール 日程は 10:40〜12:00 ワークショップ 12:00〜13:00昼食(ひょっとしたら北鷹高校家庭科クラブのみなさんの調理がでるかも) 13:20〜14:00 上映会 14:00〜15:30 トークセッション となっていますが、ワークショップをやって街中をパレードしようと思っているので、予定通りに行くかどうかは、やってみないとわからない、といういい加減なところがあります。現地主催者は多分ハラハラしながらの進行になるのじゃないかと思いますが、ま、それもまた楽し、というくらいでやりましょう。 そうそう、セノーさん、ナカタクさんも一緒に行きますので、想定外のいろんなことが起こるのではないかと楽しみにしています。 チラシができたらアップします。楽しみにしていて下さい。
ぷかぷかトピックス
障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。








