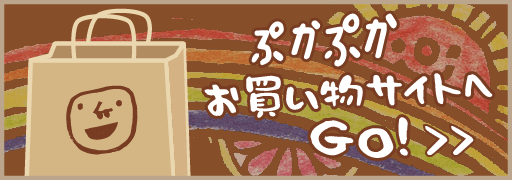1970年、横浜で脳性麻痺の子どもを母親が将来を悲観して殺してしまうという事件がありました。当時、そういう事件がたびたびあり、そのたびにマスコミは「施設がないが故の悲劇」「かわいそうな親を救え」という論調でした。横浜の事件では、子育てに疲れ絶望的になった母親への同情が地元町内会などの減刑嘆願運動となって現れました。
これに対し、脳性麻痺の人たちの運動体「青い芝の会」の横塚さんは
「重症心身障害児に生きる権利はないのか」「罪は罪として裁け」
と主張しました。「殺される側」の障害者からの発言は大きな反響を呼び、裁判では、当時としては異例の(執行猶予つき)「有罪」判決が出ました。
「施設があればあのような事件は起こらない」という世論に対し、横塚さんは、障害者を「劣った存在」「価値のない存在」とみなし、だから生きていても仕方がないと考える健常者の価値観(差別意識)こそが問題の根底にある、と指摘しました。
約50年前の話です。でも、横塚さんの指摘した、障害者を「劣った存在」「価値のない存在」とみなし、だから生きていても仕方がないと考える健常者の価値観(差別意識)は、情けない話、全くといっていいほど変わっていません。
どうして変わらなかったのか。結局のところ、障害者の側、あるいはその関係者の側からのメッセージが、健常者の意識を変えるまでに至らなかった、ということではないかと思います。もちろん、健常者自身の問題もありますが。
事件のあった1970年当時、私は学生でした。
「障害者と健常者は共に生きねばならない」「障害者と共に生きよう」
といった主張はありましたが、障害者運動に関わっていない限り、ほとんど他人事でした。「共に生きねばならない」「共に生きよう」なんて言われても、社会の理念としてはなんとなくわかる気もしますが、自分の生き方としてやっていく、というふうにはなりませんでした。
結局そういったメッセージでは、健常者の意識は変わらなかったのだと思います。個別にがんばっている人たちはいましたが、社会全体の意識は変わらなかったと思います。
50年たって、福祉の制度が整い、障がいのある人たちの暮らしやすさはそれなりの進歩があったと思います。でも、健常者の価値観はほとんど変わっていない気がします。そういう中で相模原障害者殺傷事件が起こり、犯人の主張を否定しきれない社会が頑としてあります。健常者はこの50年、何をしていたのか、ということになります。障がいのある人たちとちゃんとつきあってこなかったんじゃないかと思います。
映画『Secret of Pukapuka』の中でダウン症の子どものお母さんは、絶望の中にいて外に出られなかった、と語っていましたが、そのお母さんを絶望の中から救い出す言葉を持っているのか、と自分に問うと、いまいち自信がありません。そういう意味では、お母さんを救ったあのダウン症の赤ちゃんにはかなわないのです。
東洋英和の学生さんが「自分に障がいのある子どもが生まれたら、どんな風に思うんだろう」ってぽつんと言ったときも、学生さんにかけるうまい言葉が見つかりませんでした。
学生さんが口にした「自分に障がいのある子どもが生まれたら、どんな風に思うんだろう」の問いは、50年変わらなかった健常者の価値観の中でなおも自分を問い、そこを超える何かを見つけようともがいている感じがしました。もがいている感じ、というのはぷかぷかの映画を見たあとの学生さんの言葉だからです。映画から感じたものと、自分の抱いた不安との落差をなんとか埋めたいという思いのもがきです。
そんな学生さんがぷかぷかの取材の中で何を見つけるのか、ものすごく楽しみにしています。