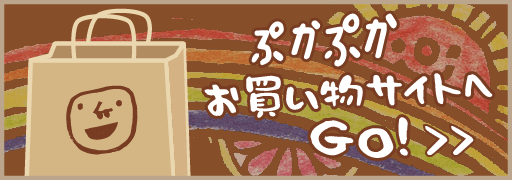小諸に「おむすび長屋」という福祉施設?があります。おむすび長屋は、もう30年ほど前になりますが、山間の廃屋を借りて、障がいのある人たちといっしょに味噌を造りながら暮らしを立てていこうというところから出発しました。その志に共感し、おむすび長屋を訪ねました。茅葺きの傾いた昔ながらの家で、なんだかホッとする雰囲気でした。コーイチローさんというおじさんが「ボーナスでたら、スナック行って、ジュース飲むんだよ」とうれしそうに語ってくれたことが未だに印象に残っています。あたたかな「暮らし」がそこにはありました。年に一度「スナック行って、ジュース飲むんだよ」うきうきしながら語るような、ささやかな楽しみもありました。
今のように福祉の制度も十分に整っていない時代でしたから、障がいのある人たちといっしょに暮らしを立てていくことは、よほどの「志」がないとできないことでした。強い「志」がないとできない事業であれば、次の若い世代に引き継げないと、15年ほど前、社会福祉法人になり、作業所とグループホームになりました。
建物は建て替えられましたが、「暮らし」のあたたかさがグループホームにはありました。そのグループホームにも「個別支援計画」なる指導体制の確立が求められ、
《地域で働き、地域で暮らす「場」が、次第に「トレーニング施設」へと様変わりしてゆくように思われます。》
と、今日届いた「おむすび通信」におむすび長屋の主・田中さんが嘆いていました。
《人のにおいのぷんぷんする連中に、しょうがねぇなあ、といいつつ、寄り添う》田中さんたちの姿勢が好きでした。そういう姿勢だったからこそ、そこでの「暮らし」「仕事」には「あたたかさ」がありました。
そんなところへ「個別支援計画」が入り込んだのです。事業をやっていく上で福祉サービスの報酬をもらう以上、やむを得ないこととはいえ、「個別支援計画」で描かれる彼らとの関係は、彼らに寄り添う、という人間くさい姿勢からはほど遠い関係になっています。
彼らに寄り添いながら、丁寧に暮らしと仕事を作ってきた田中さんたちにとっては、全く理解しがたい制度だろうと思います。福祉の世界がどういう方向を向いているかがよくわかります。
そんな中にあって尚、彼らとのあたたかなおつきあいこそ大事にしたいと私は思うのです。いっしょに生きていく、というのは、「ったくしょうがねぇなあ」といいつつ、今日もまた寄り添ってしまうような、そんなおつきあいであり、生き方ですから。